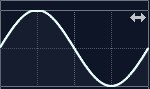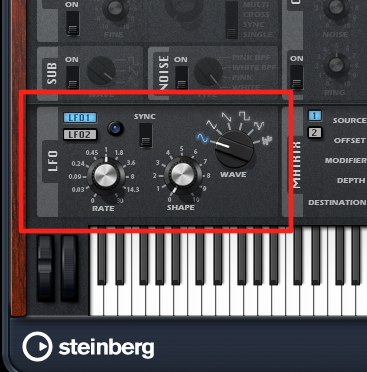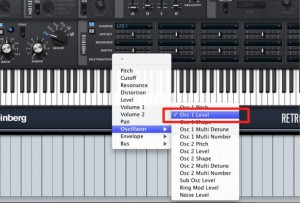LFOの基本と役割を把握する シンセサイザー 初心者講座
シンセサイザーの基本!!音に対して様々な表情を与える「LFO」
「LFO」は音程として聴こえない低周波です。
音色として使用するのではなく、
「音程」や「音色」へ変化を与えるための機能です。
このLFOを使用し、様々な音を作ることができます。
それでは詳細を見ていきましょう。
LFOを設定する
この部分が「LFO」です。
まず重要な概念です。
この「LFO」を何に対して適用するのか?を決めます。
「LFO」は実際に音が出る訳ではないため、
どこかに適用して始めてその効果が現れます。
↑ この部分から「LFO」を選択し、
「ピッチ」へ対して適用してみましょう。
↑ 適用する側(今回の場合は「LFO」)のことを「ソース」や「キャリア」と呼び、
適用される側(今回は「ピッチ」)のことを「ディレクション」「ターゲット」と呼びます。
これもほとんどのシンセに共通です。
↑ その後「Depth」を右に移動します。「LFO」の効果が強くなります。
シンセサイザーによっては「アマウント」と呼ばれます。
「サウンド」
※「Depth」を「0」〜「MAX」へ動かしています
次は「ディレクション」を「Level(音量)」に変更してみましょう。
このように音量が変化します。↓
「サウンド」
この概念が「LFO」による音作りの基本となります。
この他にもあらゆるツマミをコントロールすることができるのです。
LFOの速さ(Rate)
「LFO」の「波の形」「速さ」を変更することで
さらに細かいコントロールを行うことができます。
まずは「LFO」の速さ。
これを「Rate」呼びます。
「LFO」を「ピッチ」へ適用したサウンドは上記で確認していただきました。
その状態から、この「Rate」を回していくと
「LFO」の周期が速くなり以下のようなサウンドになります。
単位は「Hz」で1秒間に波を何回繰り返すのか?というものです。
「サウンド」
初期段階は「0Hz」のため1秒間に「0回」よってLFOの効果はありません。
右へ振り切った状態は「30Hz」で1秒間に「30回」ということです。
この「LFO」の速さを曲に合わせたいことも多々あります。
大抵のシンセサイザーには
「Sync」機能が備わっており、自動で楽曲のテンポに合わせて波を調整してくれます
「Sync」をオンにして、
何分音符で「LFO」を繰り返すのか?を決定します。
「8分サウンド」
「16分サウンド」
このように変化します。
LFOの波形
次にLFO波形です。
どのような波形を繰り返すのか?
によってその効果が変わってきます。
「OSC」で紹介した基本波形がメインになっています。
見たままの変化で「ディレクション」がコントロールされます。
目的の音がどの波形を選択すると得られるのか?
これらを把握するためにも、まずは試しサウンドを覚えてしまうことが重要です。
このような記事も読まれています
- CATEGORY:
- シンセサイザー入門講座