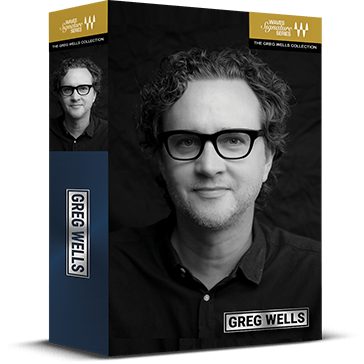【ミキシングが苦手】でも大丈夫!Waves Greg Wells Signature Series 活用術
ほぼノブ一つでクオリティの高いサウンドへ
今回はWavesのGreg Wells Signature Seriesを使用して、主要なトラックを手早くトリートメントする方法をご紹介していきたいと思います。
グレッグ・ウェルズは、アデル、ケイティ・ペリー、ミーカなど数多くのアーティストの作曲、ミックス、プロデュースに携わり、関わった楽曲の累計売上数は8500万ユニットにのぼると言われています。自身もプロデューサーとしてグラミー賞を受賞されるなど、輝かしい実績を残しています。
そんなグレッグのミキシングや音作りのエッセンスを凝縮し、トップクラスのサウンドを素早く作りたいソング・メーカー、プロデューサー、エンジニア向けに開発されたのが本シリーズ、PianoCentric、Voice Centric、Tone Centric、Mix Centricの4つです。
さて、ここに比較的ラフにミックスを行ったサンプル楽曲があります。一度聞いてみてください。
まだまだブラッシュアップの余地があるといった感じですね。
では、これにシリーズ4つのプラグインを、4つのトラックのみに足してみた結果を、聞いてみてください。
いかがでしょうか?一気に完成度が高まっていますね。
実はこれらのプラグイン、非常にシンプルな操作でここまで持ち込むことができます。
それでは、各プラグインの詳細を見ていきましょう。
Waves Greg Wells Signature Series 動画
製品の購入はこちら
アフリエイトリンクを含みます
Greg Wells Piano Centric
まずは、Piano Centricから見ていきましょう。
中央のノブを右に回すと、オープンでクリアなサウンドになっていきます。やや明るめのサウンドから、ハードなアタック感のあるピアノまで、幅広く対応可能といった感じです。
内部的には、EQやコンプなど複数のエフェクターが組み合わせられているように感じます。
右に回していって、コンプがきつくかかっているように感じるなら、インプットレベルをチェックしてみてください。ここが赤に点灯しているなら、想定よりも大きめに入力されていると考えられます。もちろん楽曲によっては狙ってそうするのもアリですが、そうでなければ、インプットを下げて、相応にアウトプットを上げてみましょう。
逆に、ノブを0より左に回していくと、ローファイでモノラルに近づいていくような効果を得ることができます。
ノブ一つなので、オートメーションで変化させるといった使い方も簡単ですね。
追加のエフェクトとして、ディレイとダブラーも装備しています。
ディレイはソースのサウンドを邪魔しない比較的ダークなトーンとなっています。
ピアノにダブラーというのも意外な感じがしますが、これはピアノに最適化されているとのことで、意外にも使えるエフェクトです。ほんのりかければピアノの響きがより複雑で豊かになりますし、強めにかけてエレピのようなサウンドを狙うことも可能です。
Greg Wells Voice Centric
続いては、Voice Centricです。
基本的な作りはPiano Centricと同じで、中央の大きなノブでサウンドをコントロールします。右に回すほど効果が強まるのが基本ですが、途中にサウンドの傾向が変わるポイントもあるように感じます。
序盤はEQで明瞭感が出てきて、中盤を超えるとサチュレーションとコンプがしっかりと効き始め、回し切るとさらにサチュレーション効果が際立って出てくるようです。
ジャンルに合わせて使い分けたり、曲のセクションに応じてオートメーションしたりといった活用ができそうですね。
またこちらも、しっかりEQやサチュレーションをかけてコンプを抑えたい場合は、インプットを下げることで対応することができます。ゲインリダクションメーターも付いているのでわかりやすいですね。
操作する際は、理屈はさておいて音に集中し、楽曲や声にマッチしたスイートスポットを探す感覚で値を決めるといいでしょう。見た目に惑わされないことから、耳を鍛えるのにも役立ちます。
また、このような模範的なサウンドを軸に据え、他のトラックもミックスしていけば、初心者にとって破綻する確率が低くなるとも言えます。
さて、付属された3つのエフェクターも加えてみましょう。ディレイ、ダブラー、リバーブとボーカルにとってはお馴染みの3種類ですね。つまみ一つなので自由度は低いですが、絶妙に使いやすい設定になっていますので、ささっと音を作りたい際には十分対応できます。
リバーブやディレイはやはりダークな印象で、素材を引き立てますね。ダブラーは思ったより繊細な聴き方で使い回しがよく、しっかり回せば左右の広がりも出るので、コーラストラックなどにも使えそうです。
このようなプリセット的なエフェクトは、初心者にとってはお手本になりますし、慣れたら他のエフェクトでしっかり作り込めばいいでしょう。
Greg Wells Tone Centric
続いては、Tone Centricです。
Toneと名前が付いていますが、音の明暗ではなく、チューブサチュレーションやテープサチュレーションの感覚に近いエフェクトで、グレッグ自身が愛用するアナログ機器をベースにモデリングされているとのこと。
中央のノブを右に回すと、アナログの風合いが出てきて、倍音付加効果を得ることができますが、単純に効果が強くなるだけでなく、ノブの位置によってキャラクターが異なるようです。
中盤までは中低域のふくよかさが増していく感じがありますね。さらに回していくと高域がきらびやかになってきます。90辺りを過ぎると、途端にアナログの飽和したような感じが出てきますね。こちらもしっかりと耳をこらしながら、楽曲に合うスイートスポットを探していきましょう。
また、インプットの調整も重要です。もしインジケーターが緑点灯(または無点灯)ならば、これを黄色点灯になるくらいまでにインプットを上げてみましょう。この際、インプットとアウトプットのリンクが便利です。
緑→黄色に変わると、効果がより顕著になったように感じます。どちらのサウンドが合うかは、楽曲の雰囲気や他のトラックとの関係で決めていきましょう。
シンプルながら奥深いエフェクターだと思います。
Greg Wells Mix Centric
最後の仕上げは、マスタートラックに適用するMix Centricで行います。
Mix Centricでは、ノブ一つで、複数のEQやコンプ、倍音歪みが複雑に組み合わされ、現代的なマスタリングサウンドに仕上げてくれます。
もちろんこれ一つで何もかも解決と言ってしまうと眉唾かもしれませんが、楽曲にハマればこの手軽さからは考えられないような結果をもたらしてくれるので、とにかくスピード優先の際や、マスタリングが苦手といった方などはきっと重宝するはずです。
中央のノブを右に回していくと、 明瞭感・音圧ともに上がっていき、適度にコンプも聞いてきます。ゲインリダクションも参考にしてください。
しっかりEQや倍音歪みを効かせ、コンプレッションを控えめにしたい場合は、インプットを下げて、相応にアウトプットを上げるといいでしょう。
逆に、あまりサウンドを明るくしたくはないがコンプ効果を得たいという場合は、ノブを左に回し、インプットを上げてアウトを下げます。INTENSITYの値が低くても、ゲインリダクションが反応するようになるはずです。
このMix Centricも、シンプルながらノブの位置とインアウトの組み合わせで、意外とバリエーション豊かな音作りが可能です。個人的には、このキャラクターをマスタリングの一つのプロセスとして組み込むのもアリなのではないかと思います。
以上今回は、Greg Wells Signature Seriesを取り上げましたが、今回改めて使ってみて、思った以上に使いでのあるプラグインだなと再確認しました。
ハマってしまえば一つで済むこともありますし、少し他のプラグインで手を加えて仕上げるといった使い方もできます。
また、モデル的なサウンドとして聞き馴染んでおくことで、ミックスやマスタリングのスキルアップにも繋がるかもしれません。
気になった方はぜひ、デモからでも使ってみていただければと思います。
製品の購入はこちら
アフリエイトリンクを含みます
スピードを優先したい、ミックスで悩んでいる方にオススメ!
「WAVES Greg Wells Signature Series」✍️3つの特徴
1.グラミー賞受賞プロデューサーのGreg Wells氏とWave社との共同開発
2.ワンノブ仕様で簡単操作
3.ピアノ、ボーカルなど、4つのプラグインを使い分け詳細:https://t.co/LetjFaCu7x pic.twitter.com/3hgJV2vGdy
— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) June 13, 2020
記事の担当 大鶴 暢彦/Nobuhiko Otsuru