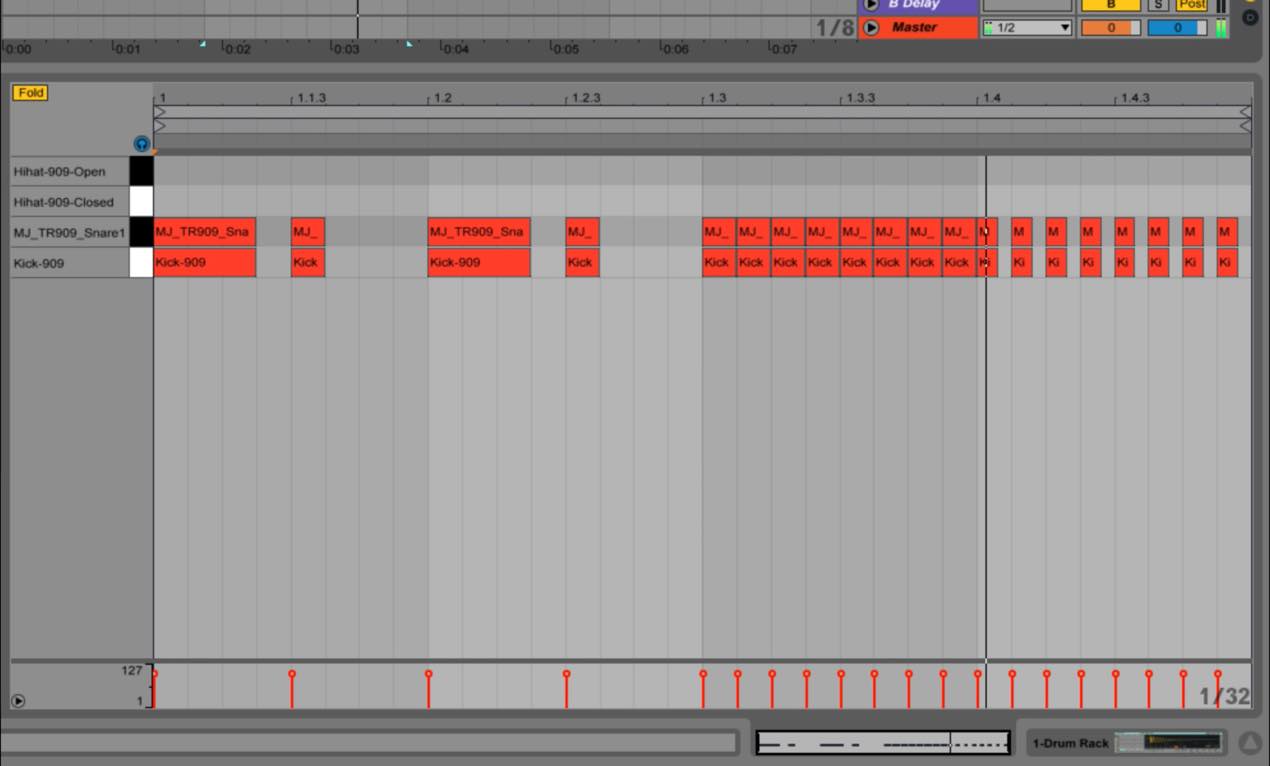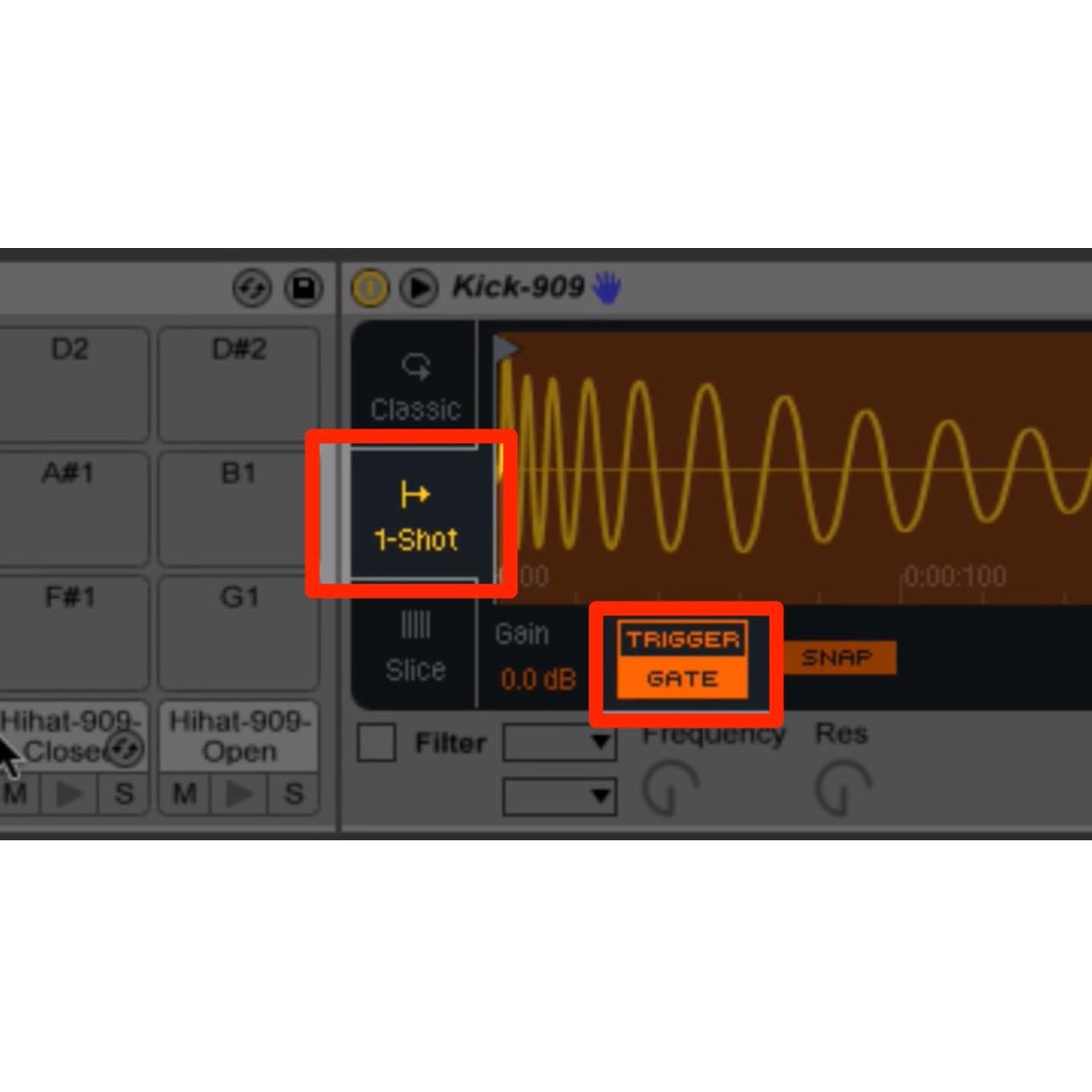Impulseでドラム連打をコントロールする Ableton Live Tips
連打時に必須の”余韻”のコントロール
EDMやダンス系の楽曲でよく使用される、スネアやキックの連打を打ち込む際、
「速くなると音がかぶってアタックが分かりにくくなる」「1-Shotにするとノイズが入る」
といった問題にぶつかったことはないでしょうか?
Ableton LiveのImpulseを使えば、余韻を自由にコントロールし、
連打に最適なドラムサウンドをデザインすることができます。
それでは、方法を見ていきましょう。
製品の詳細ページへ
まず、以下のような連打を打ち込んだとします。
これをDrum Rackのデフォルトの状態で鳴らすと、ノートの長さは関係なく、
すべての余韻が終わりまで完全に再生されます。
これも悪くはないのですが、32分音符等のかなり早い連打では、余韻と次の音がかぶって、
音のキレが悪くなってしまうことがあります。
その際にまず行っていただきたい設定が「1-shot」です。
キックやスネアのパッドを選択し、右に表示されるSimplerで、
「Classic」となっているところを「1-Shot」とします。
併せて、「TRIGGER」となっているところを「GATE」に変更すると、
ノートの長さに従って余韻がカットされ、速い連打でも次の音にかぶることはなくなります。
しかし、一部のサンプルでは強引に切りすぎて、連打の際に
「プチプチ」というノイズが発生することがあります。
そこで使用していただきたいのが、以前のTipsでもご紹介したImpulseです。
Impulseのパラメーターには「TRIGGER」「GATE」を切り替えるスイッチがあり、
更にその上に「Decay」というツマミがあります。
それぞれのモードの特徴と、Decayの効き方は以下のとおりです。
- TRIGGER
- GATE
打ち込みノートの長さに関係なくDecayで設定した長さを常に再生します。
打ち込みノートの長さに従って再生が止まり、Decayで設定した長さ分の余韻を残します。
「GATE」モードでDecayを適切な数値に設定すれば、Drum RackのGATEのように
「プチプチ」ノイズが発生することはなくなります。
Impulseはその他にも、サチュレーターやフィルターなども備えており、
ドラムサンプラーとして非常に使い勝手が良いものです。
それら機能の中でも特に面白いのが、右下のRamdomボタンで、
パンをランダムに振り分けることができます。
連打の際に組み合わせると面白いかもしれませんね。
ぜひ、いろいろな使い方を研究してみてください。
製品の詳細ページへ
このような記事も読まれています
EDM ハイハットの打ち込みテクニック
ハットを左右に分けて配置することで、様々なグルーブ感を演出することができます。その一例を解説していきます。
ドラムパターンのマンネリ化を防ぐテクニック
ドラムの打ち込みで陥りがちなのが、短いパターンをひたすらループすることで、変化が乏しくなってしまうということです。ここでは、パターンに対して簡単なエデットを行うだけで、ドラムのマンネリ化を防ぐテクニックをご紹介していきます。
効率的なベロシティ設定術 Ableton Live Tips
個別に一つ一つ行うのは少し手間がかかります。ここではベロシティを簡単に一括調整する方法をご紹介します。
Impulseを使ってハイハットのキレを出す Ableton Live Tips
ハイハットのオープンとクローズが重なってドラムのキレが出ない、といった際にはImpulseの「LINK」機能です。互いの音が同時に鳴らないよう、簡単に設定することができます。
- CATEGORY:
- Ableton Live Tips