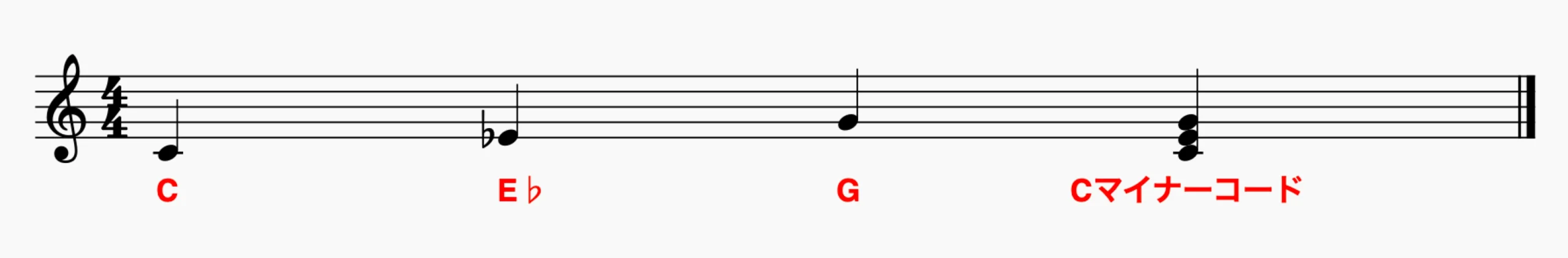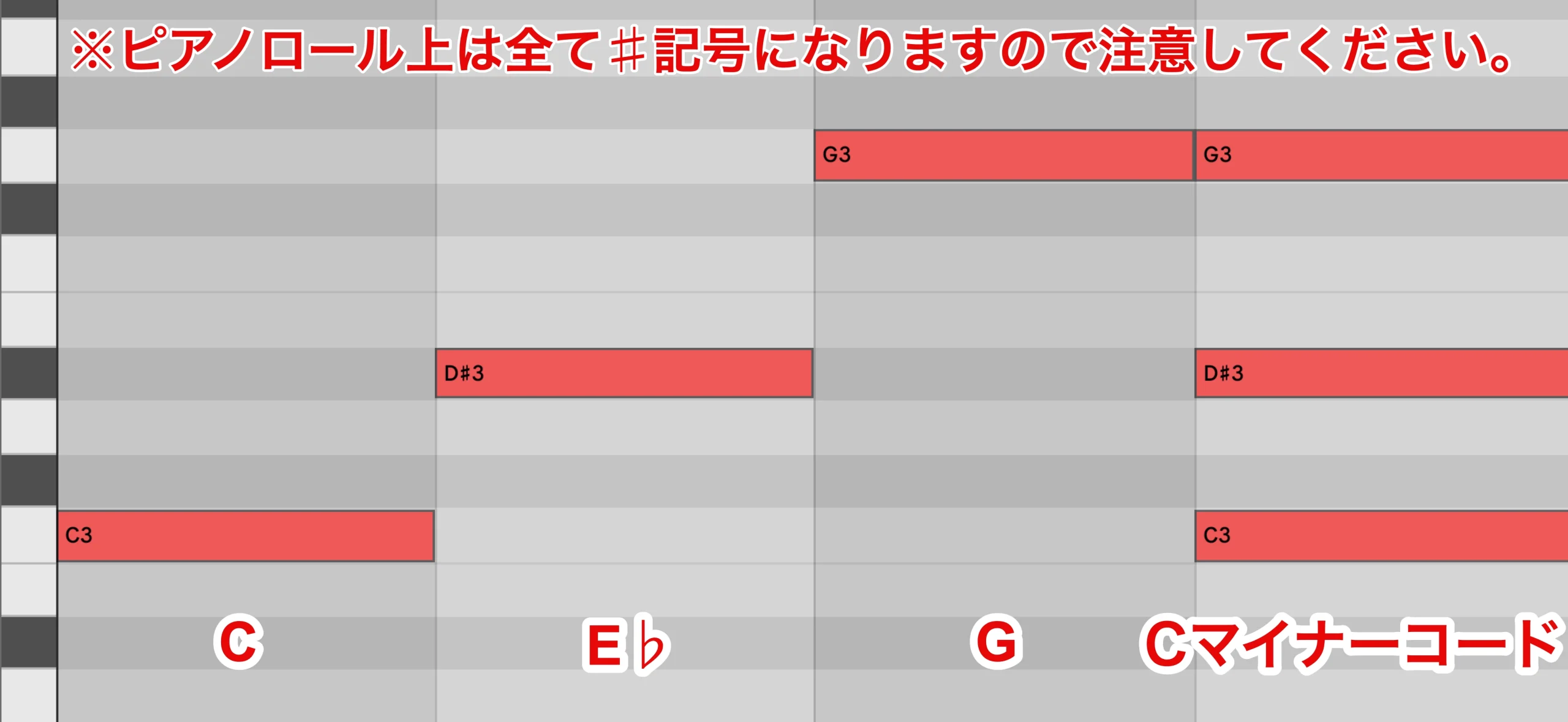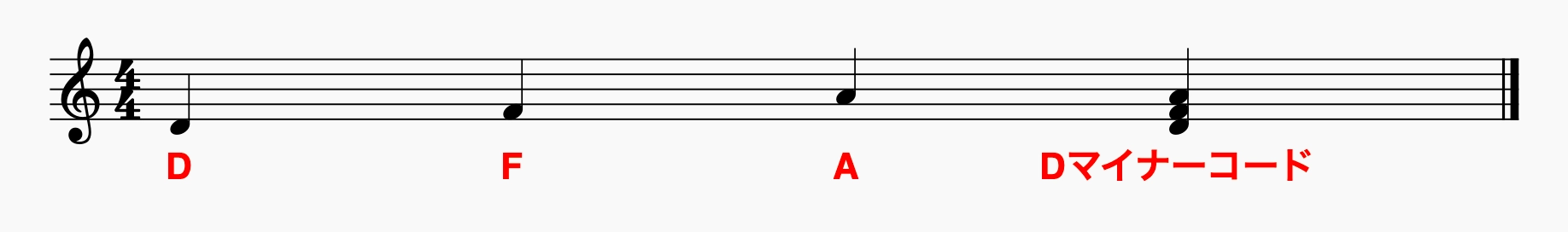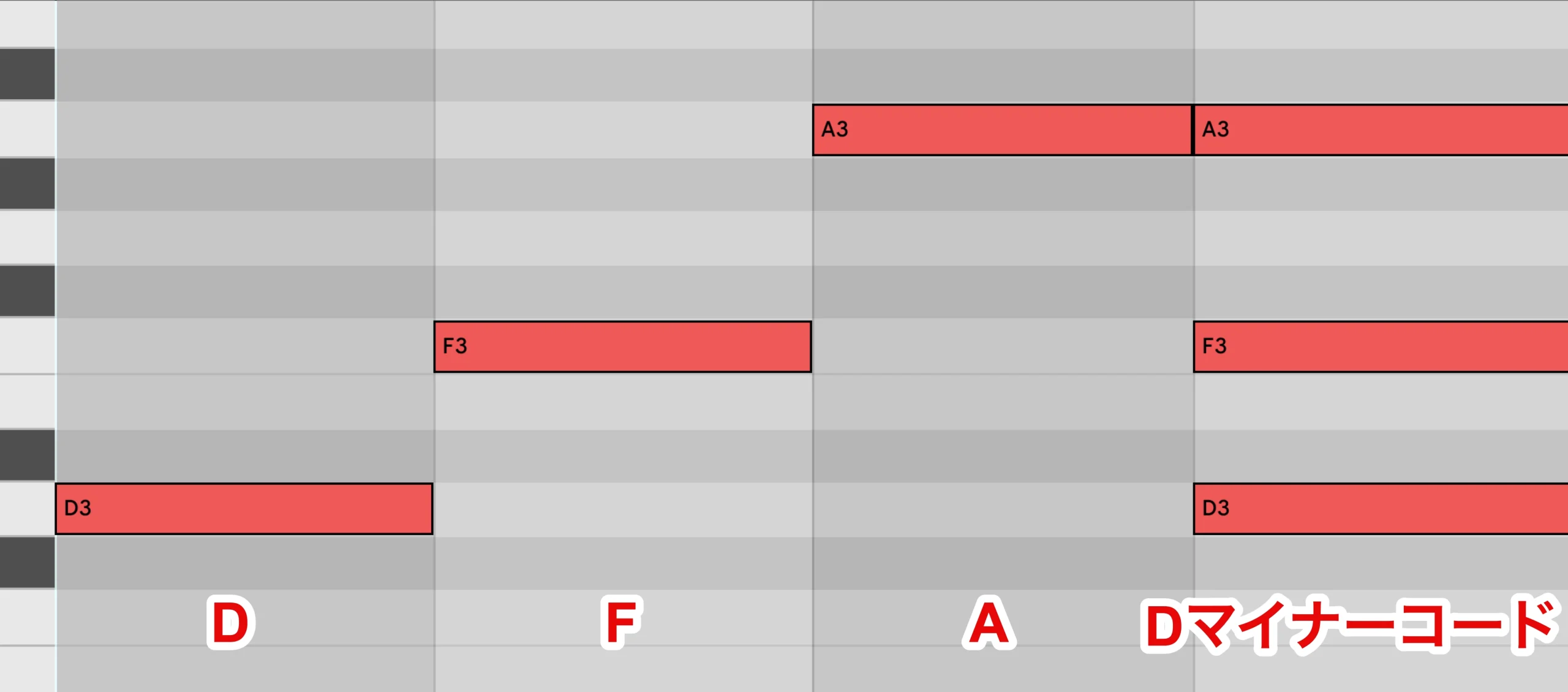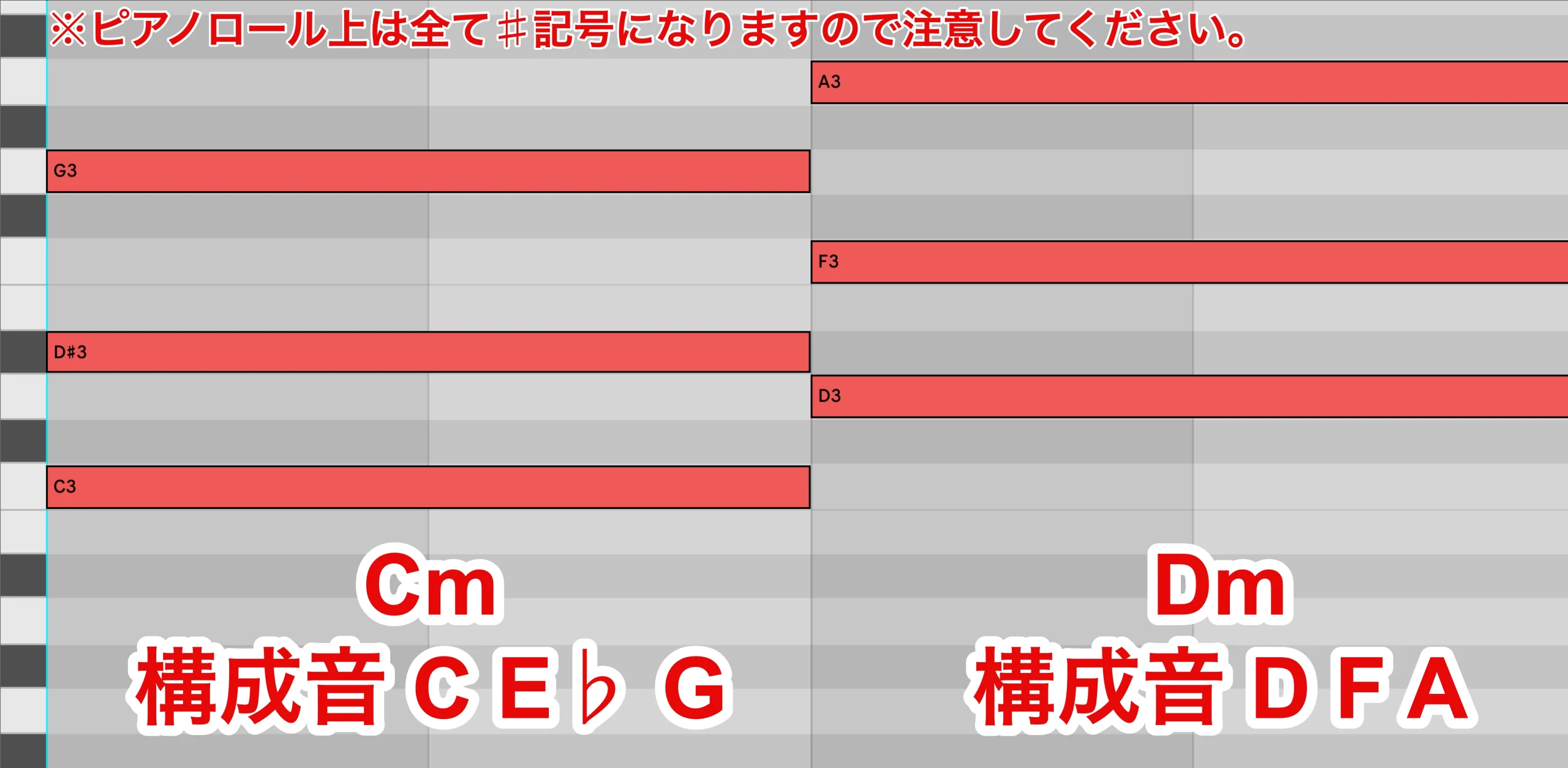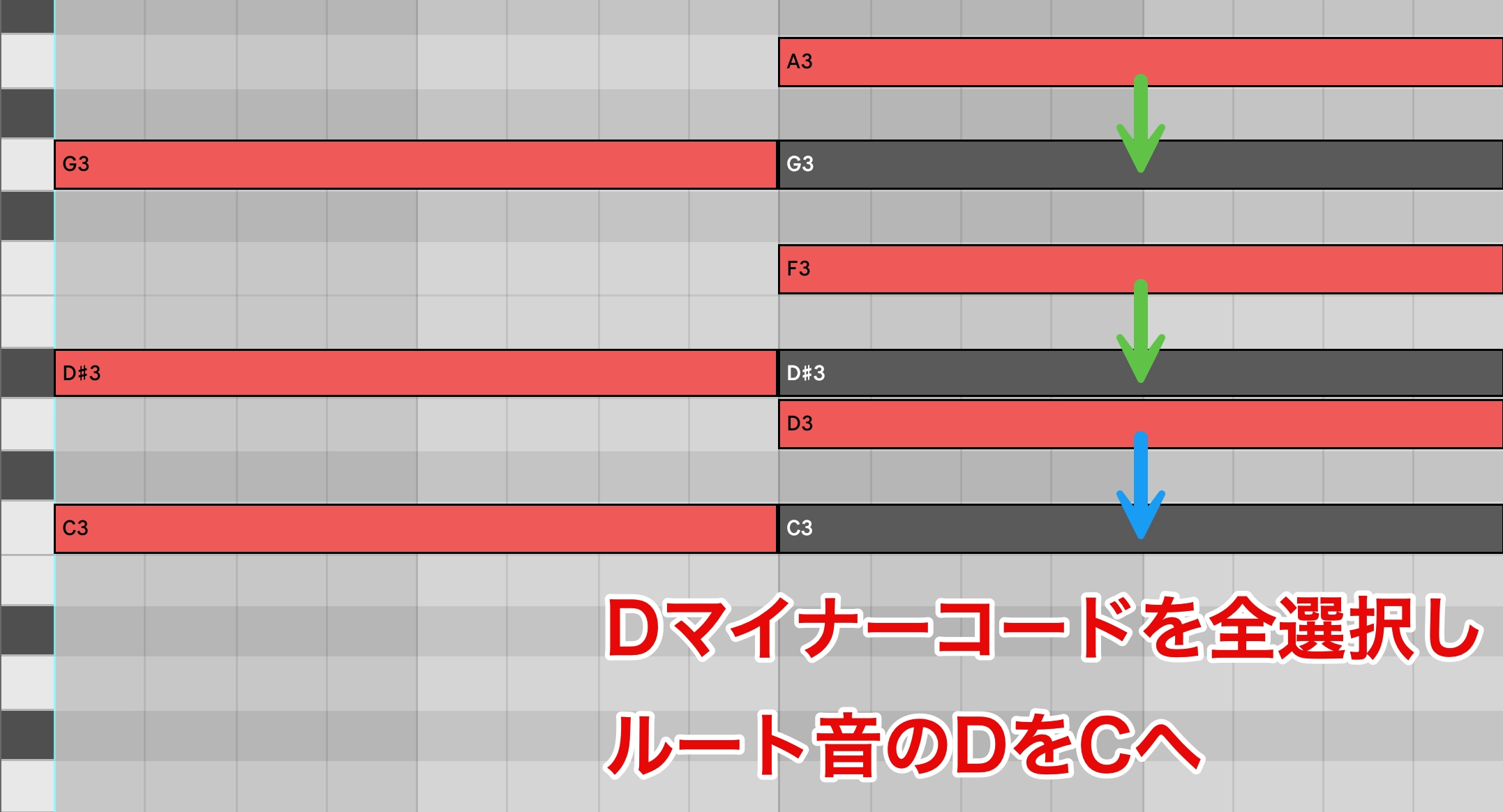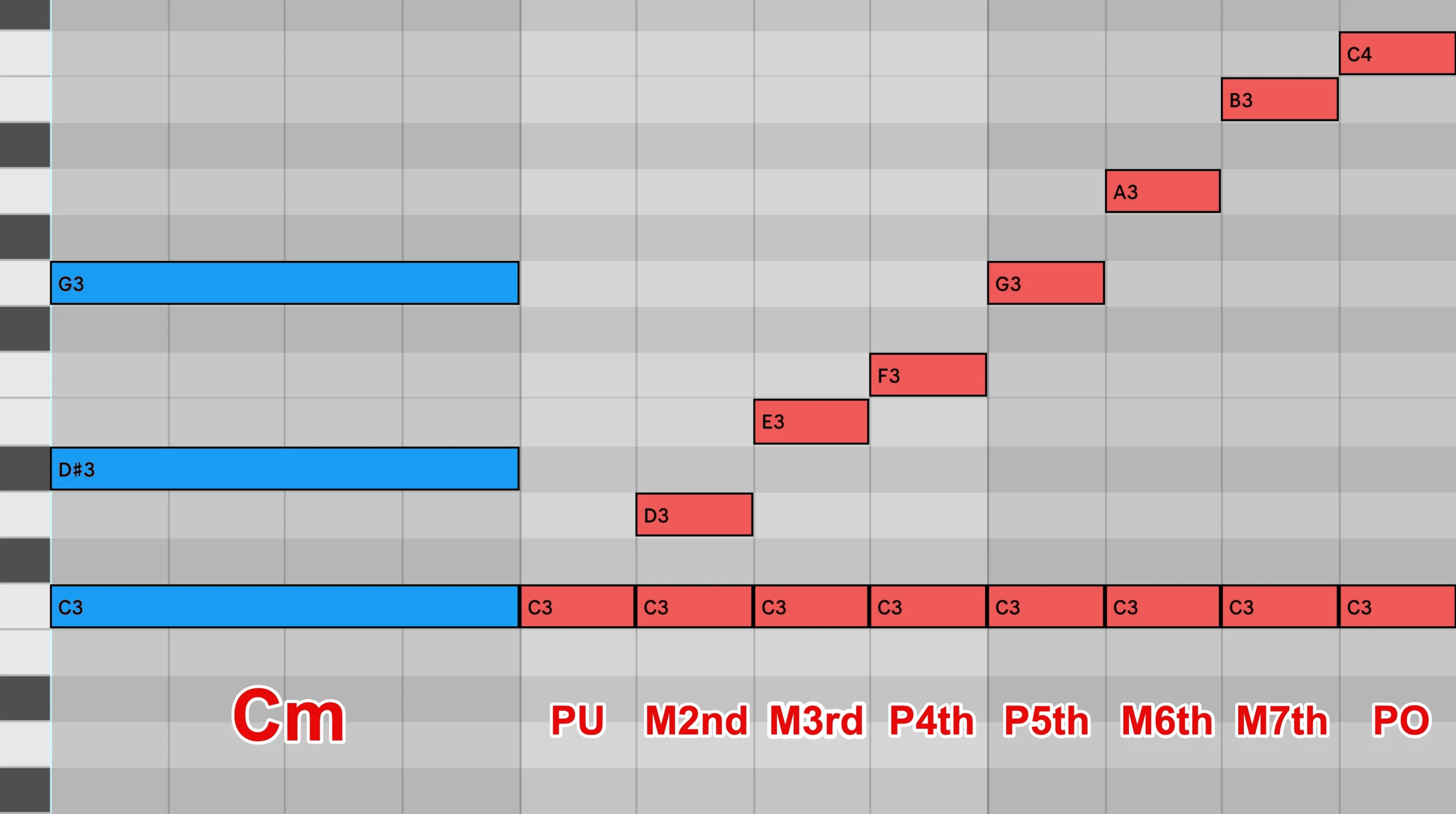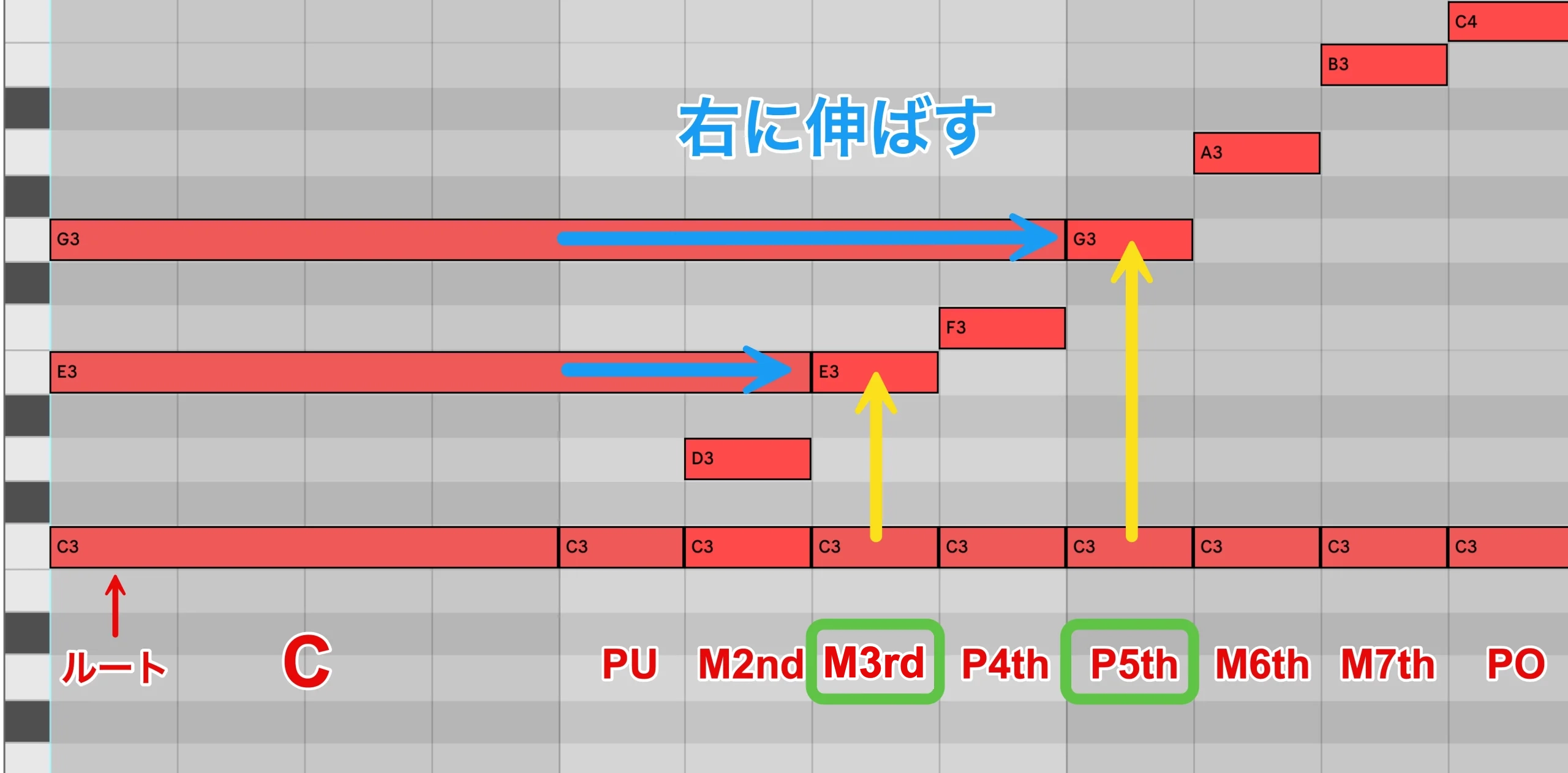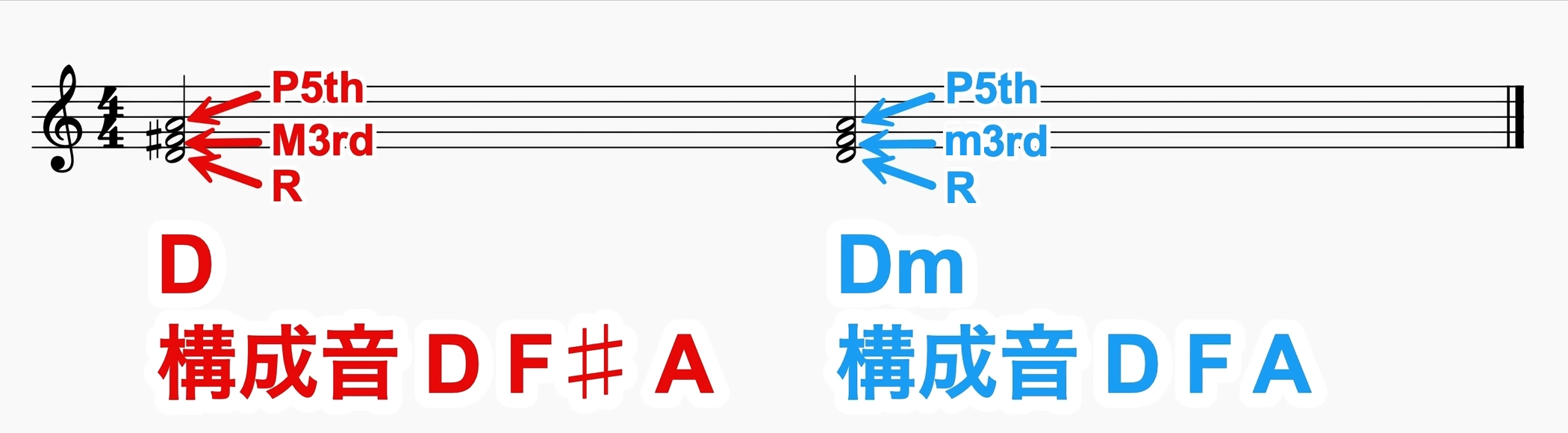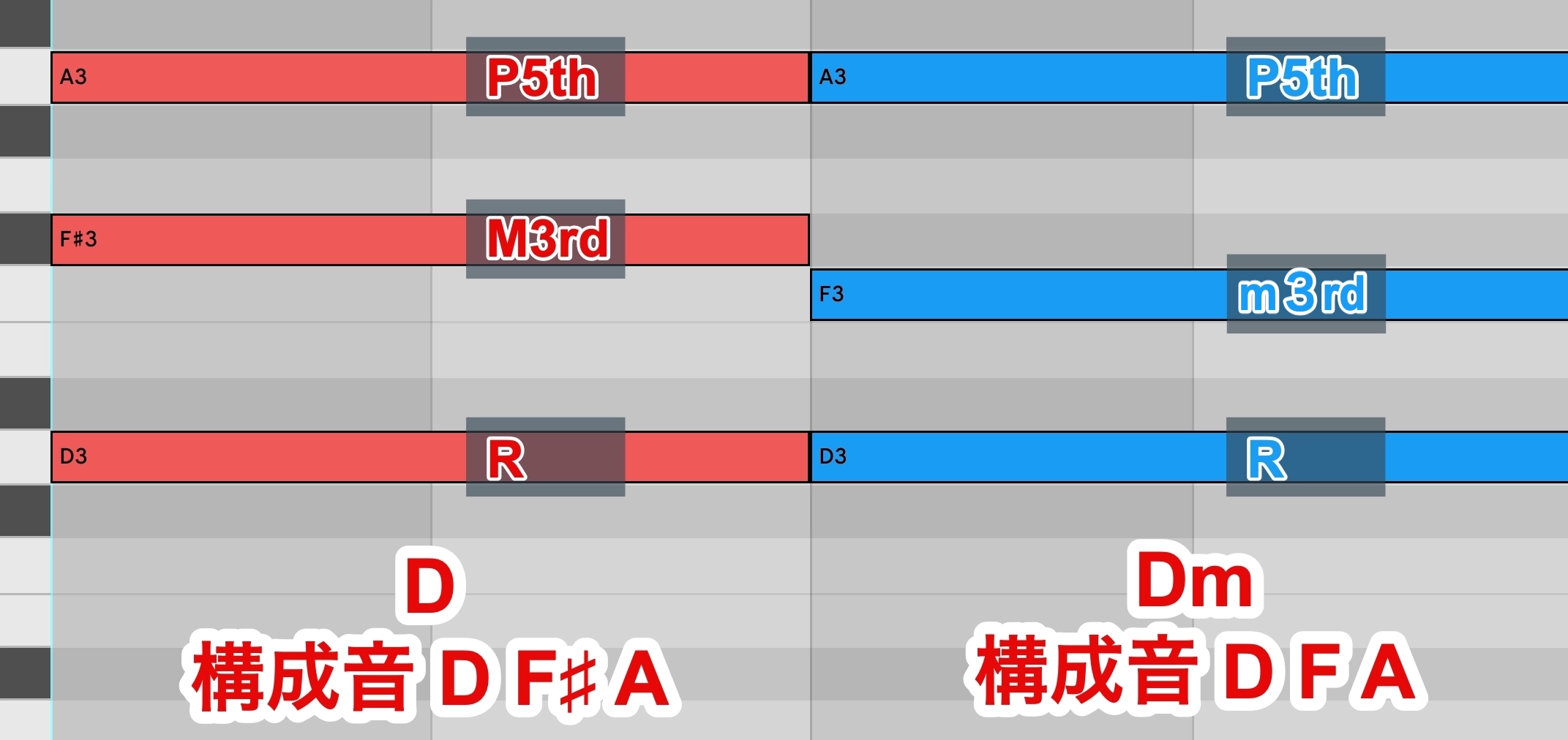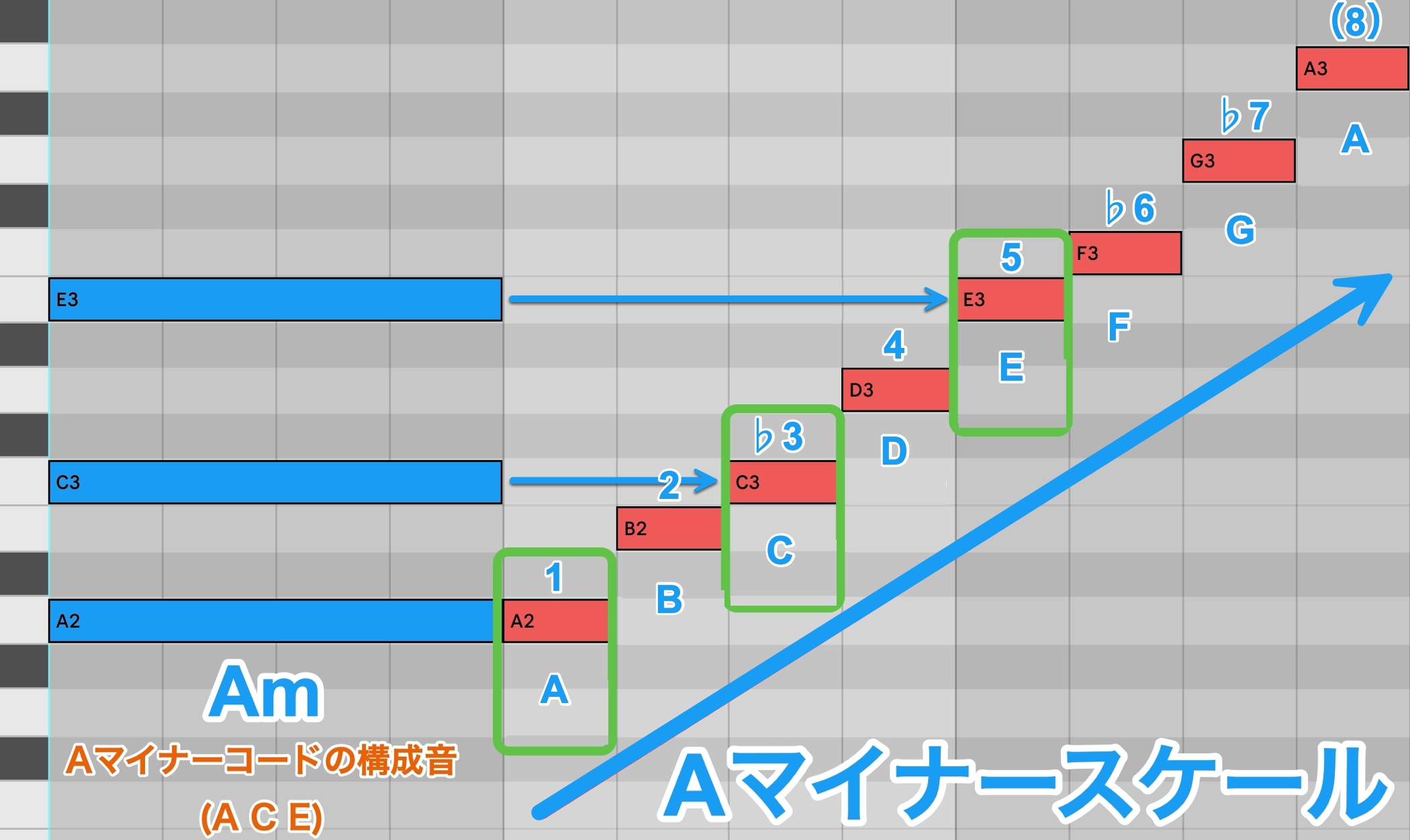三和音(トライアド)のマイナーコード/音楽理論講座
メジャーコードの法則を少し変えるだけでマイナーに
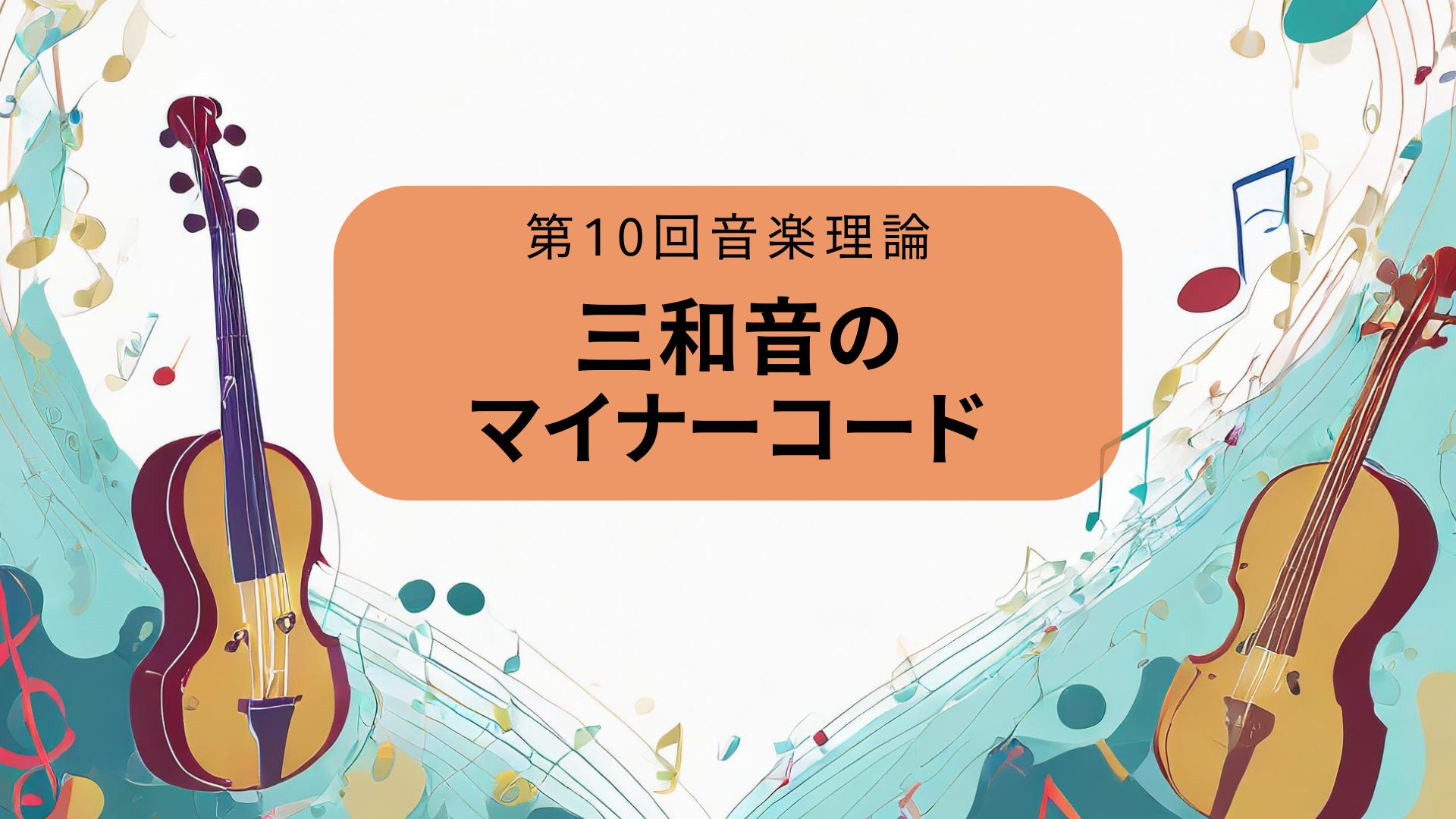
前項では、メジャーコードの作り方を確認しました。
今回は、これまで何回か出てきました、暗い雰囲気を持つコード「マイナーコード」を見ていきます。
実は、前項のメジャーコードを把握していると、各マイナーコードはすぐに弾けます。(マイナーに限らず、他のコードにも言えます。)
それでは、まず「Cマイナーコード」のサウンドを聴いてみてください。
コード構成音を鳴らした後に、コードが鳴ります。
マイナーコードは下記のように表記される場合が多いです。
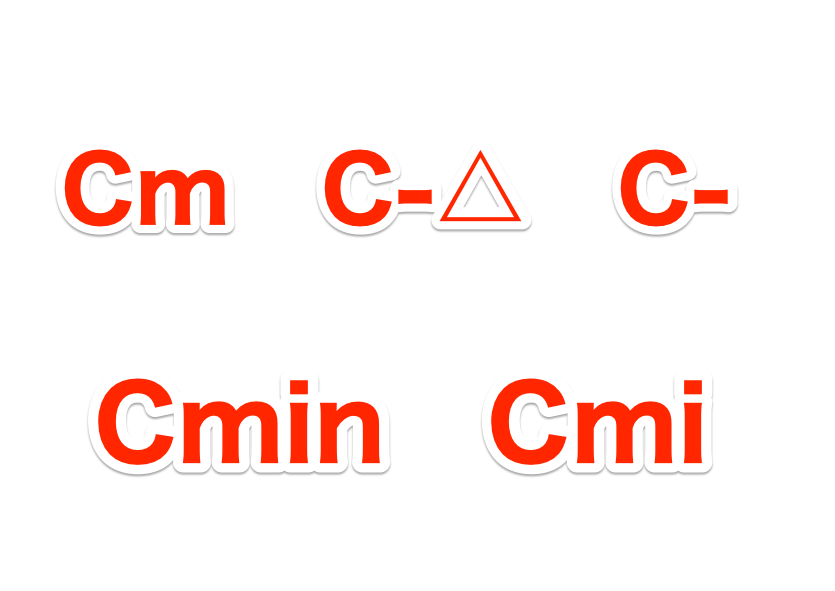
一般的なものとして、
- Cマイナーコードなら「Cm」
- Dマイナーコードなら「Dm」
のような表記でしょうか。
譜面とピアノロールで確認してみましょう。
前項で学んだ、ルートの「C」に「Eb」と「G」が重なっていますね。
さて、それではのDマイナーコードも確認してみましょう。
構成音は下記となります。
「Cマイナーコード」と「Dマイナーコード」の作り方、構成音は分かりました。
前回のメジャーコードと同様に、双方を比較してみましょう。
Dマイナーコードを全選択後、ルート音のDをCまで動かしてみましょう。
両方とも同じ、Cマイナーコードになりましたね。
マイナーコードの基本形も、重ねる音に法則がありそうです。
ここで、マイナーコードがどのようにできているのか。
ルート音にどのように重ねているのかを確認してみます。
メジャーの時と同様に、Cマイナーコードの隣にインターバルを用意してください。
Cをルートとして、その上に重ねたE♭とGを右に伸ばしてみましょう。
メジャーコードは、R,M3rd,P5thでしたね。
マイナーコードは、M3rdが半音下がり、m3rdになっていますね。
メジャーコードのM3rdを半音下げて、m3rdにすると、明るい雰囲気のメジャーコードから暗い雰囲気のマイナーコードに変化しました。
サウンドも確認します。
「Cメジャー→Cマイナー」
そういえば、「Dメジャーコード」の構成音は「D/F#/A」でした。
上記法則を使えば、簡単にDマイナーコードを作ることができますね。
「M3rd」を半音下げて、「m3rd」に変更すればOKです。
サウンドは以下です。
メジャーコードと、マイナーコードの違いがわかってしまえば、メジャーコードの知識を生かして、すべてのマイナーコードの構成音にもたどり着けます。
併せて、スケールディグリーでも確認しておきましょう。
前回のメジャーコードが「1/3/5」でしたので「1/♭3/5」となりますね。
白鍵だけでわかりやすかった「Aマイナースケール」で試してみましょう。
まとめると、マイナーコードの基本形は
- インターバルで覚えるなら
「R/m3rd/P5th」✴︎ルートはRとします。 - スケールディグリーで覚えるなら
「1/b3/5」
となります。
次回は、ディミニッシュコードを見ていきましょう。