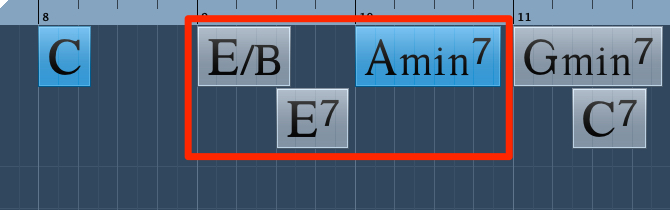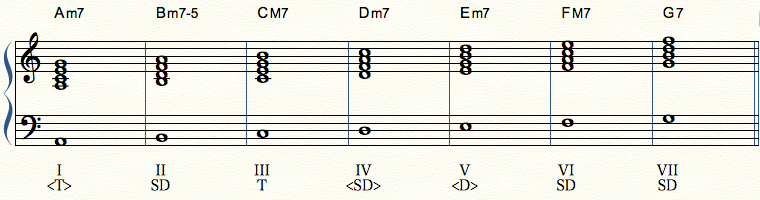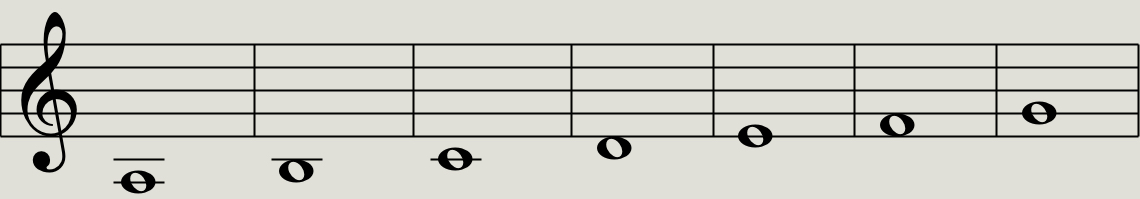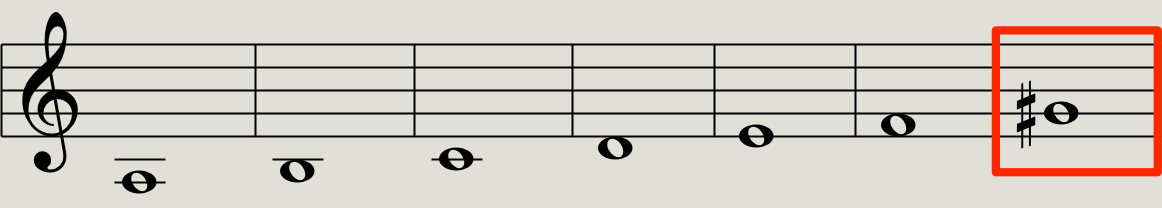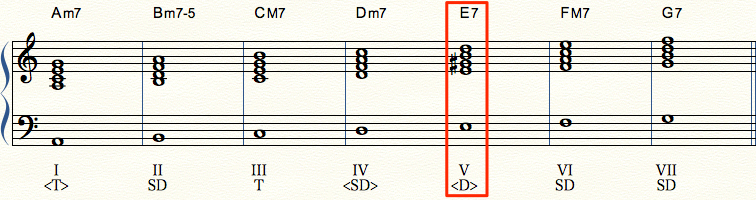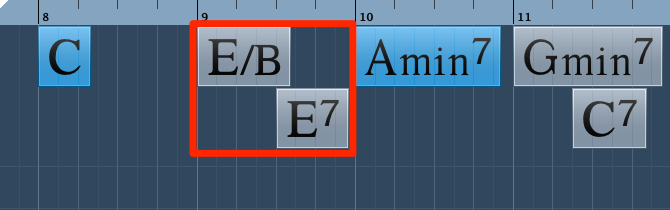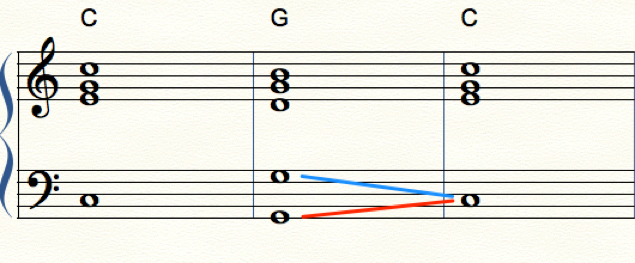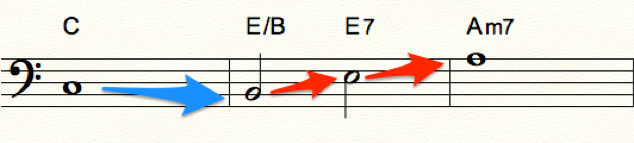いきものがかり「ありがとう」コードアナライズ_3 ノン・ダイアトニックコード
ノン・ダイアトニックコードと強進行に注目する
いきものがかりの「ありがとう」のコードアナライズ第3弾です。
今回は、「ノン・ダイアトニックコード」と「ベースの強進行」にスポットを当ててみたいと思います。
解説対象楽曲
解説動画
1_キーの判別方法
2_コード進行
3_ノン・ダイアトニックコードについて(当記事となります)
4_ツー・ファイブについて
5_ピボット・コード
6_ダブルドミナントとサブドミナントマイナー
7_分数コード(オン・コード)について
セカンダリー・ドミナント(副次ドミナント)とは何か?
ノン・ダイアトニックコード(借り物コード)が現れたら、
次に繋がるコードとの関係性を調べてみましょう。
ここでは、E7(E/Bも同一と考えます)→ Am7ですので、
Am7がトニック(主和音)となるスケール、Aマイナースケールのダイアトニックコードを考えてみます。
「A ナチュラル・マイナースケール」
「A ハーモニック・マイナースケール」
マイナースケールは、用途により変身していきます。
コードを考える時には、スケールの7番目の音を半音高く変化させた、
ハーモニック・マイナー(和声短音階)スケールを用いることがあります。
Aマイナー・ハーモニックマイナースケールですと、GがG#となります。
ここで、一番重要なのは、5番目つまり「ドミナント」コードが変化することが、ポイントです。
(ちなみにドミナント以外のGを含むコードも、G#を用いることもありますが、必ずしもとは限りません)
つまり、E/B→E7→Am7だけを考えると、
Aマイナーのキーの「V(ドミナント)」から「I(トニック)」のコードの進行になっています。
ここで、Aマイナーのキーに転調したとも言えるのですが、
ただ一瞬だけですので、転調というには大げさなので、
一時的にAマイナーのキーから和音を借りてきたと言った方がふさわしいでしょう。
このような、関係性の深いキーから一時的に借りてきたドミナントの和音を「セカンダリー・ドミナント」と呼ばれます。
「セカンダリー・ドミナント」についての、より詳しい解説は、リハーモナイズ講座の方にありますので、そちらも参照ください。
ベースの強進行に着目しよう
E/B→E7は、コードとしてはどちらも「E」ですが、E/Bは、ベース音を「B」にするという意味です。
同じコードが続くところも、転回させてベース音を変えているのがポイントです。
ドミナントの和音から、トニックの和音に進行する場合、
ベース音は「4度上行(あるいは5度下行)」します。
コード進行の中でも、特にパワフルなベース音の進行で「強進行」とされています。
ここでは、「E/B」という転回型を使ってベースにBをもってくることで、B→E→Aとなり、
4度の強進行が2回続くので、よりAm7に辿り着いたときに、強烈な達成感を感じます。
冒頭のCからBが、半音下降で緩やかな進行で、
その後の2段階の強進行なので、そのコントラストが際立っています。
記事の担当 侘美 秀俊/Hidetoshi Takumi

武蔵野音楽大学卒業、映画/ドラマのサウンドトラック制作を中心に、数多くの音楽書を執筆。
オーケストレーションや、管弦楽器のアンサンブル作品も多い。初心者にやさしい「リズム早見表」がSNSで話題に。
北海道作曲家協会 理事/日本作曲家協議会 会員/大阪音楽大学ミュージッククリエーション専攻 特任准教授。
近年では、テレビ東京系列ドラマ「捨ててよ、安達さん。」「シジュウカラ」の音楽を担当するなど多方面で活躍中。
☟☟著書/作品は下記リンクから☟☟