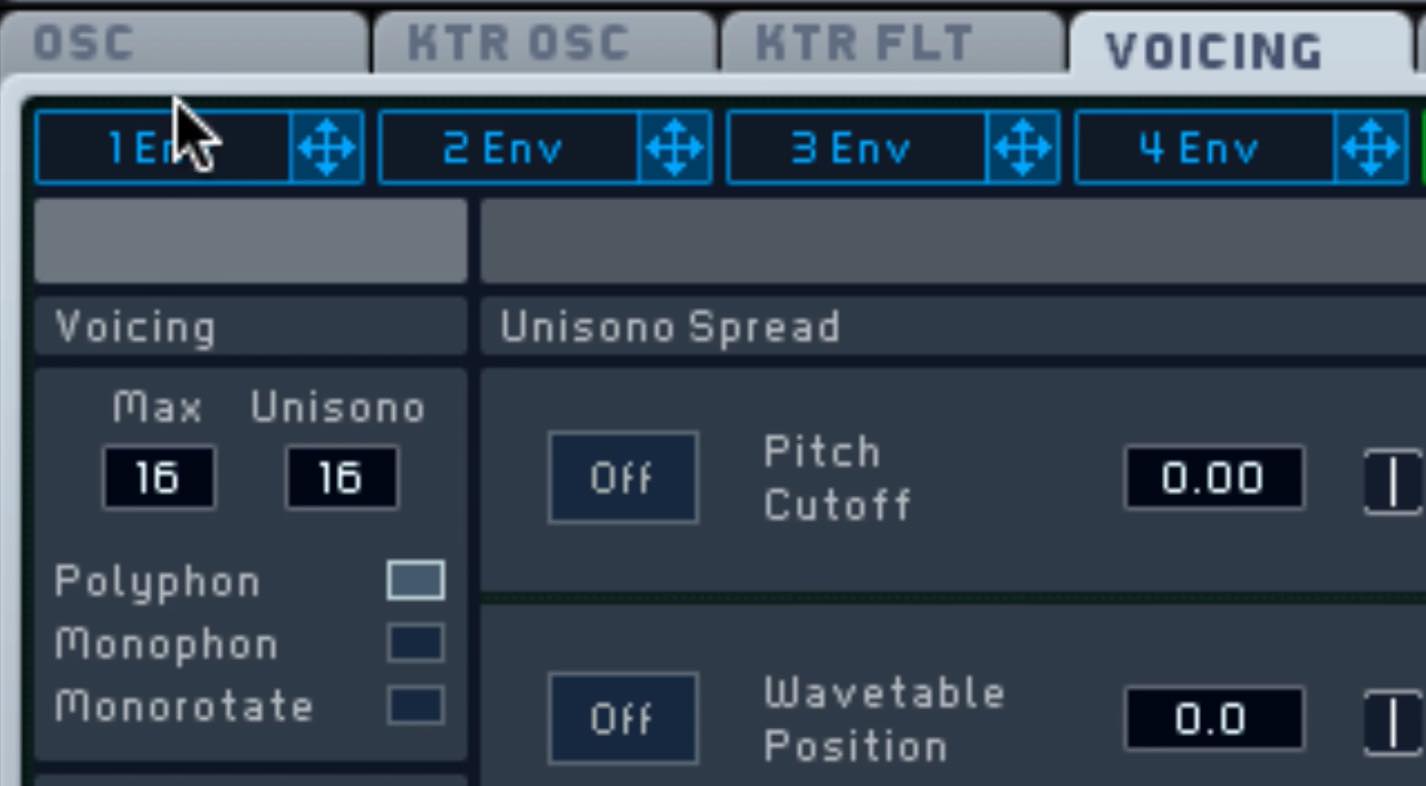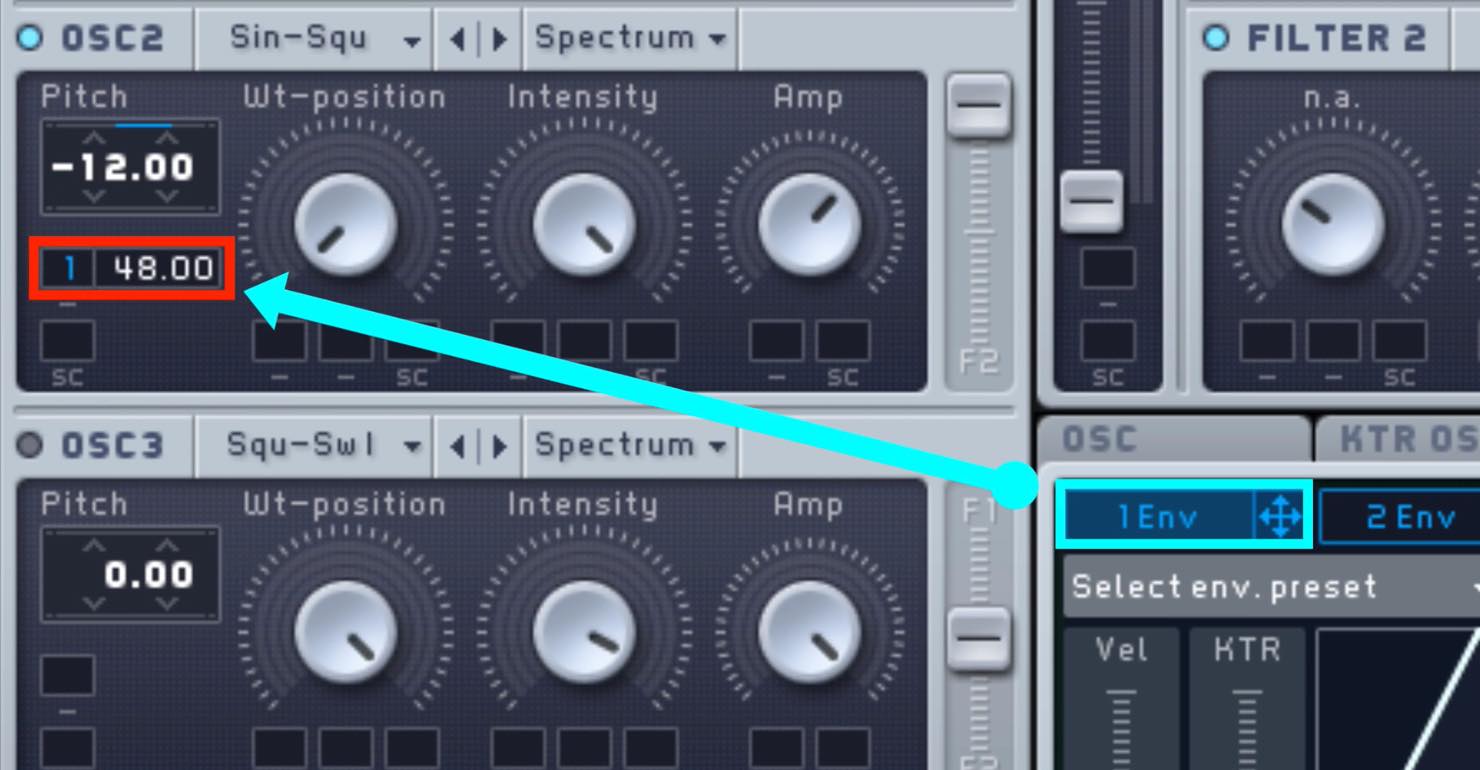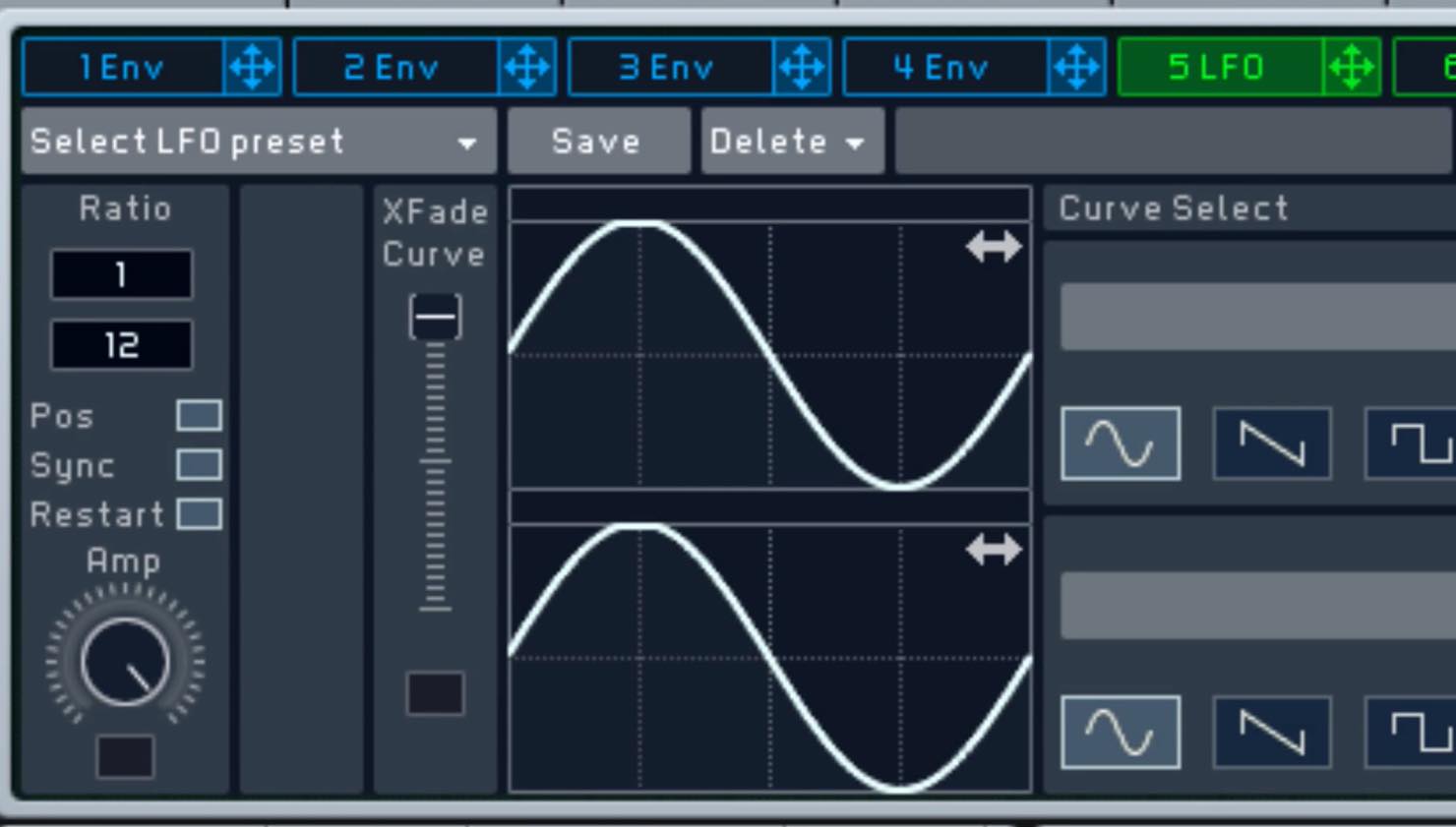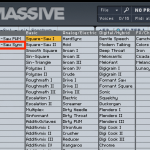Skrillexのようなワブルベースを作る 金属的な音の作り方
ワブルの間に織り交ぜると効果的なメタリックサウンド
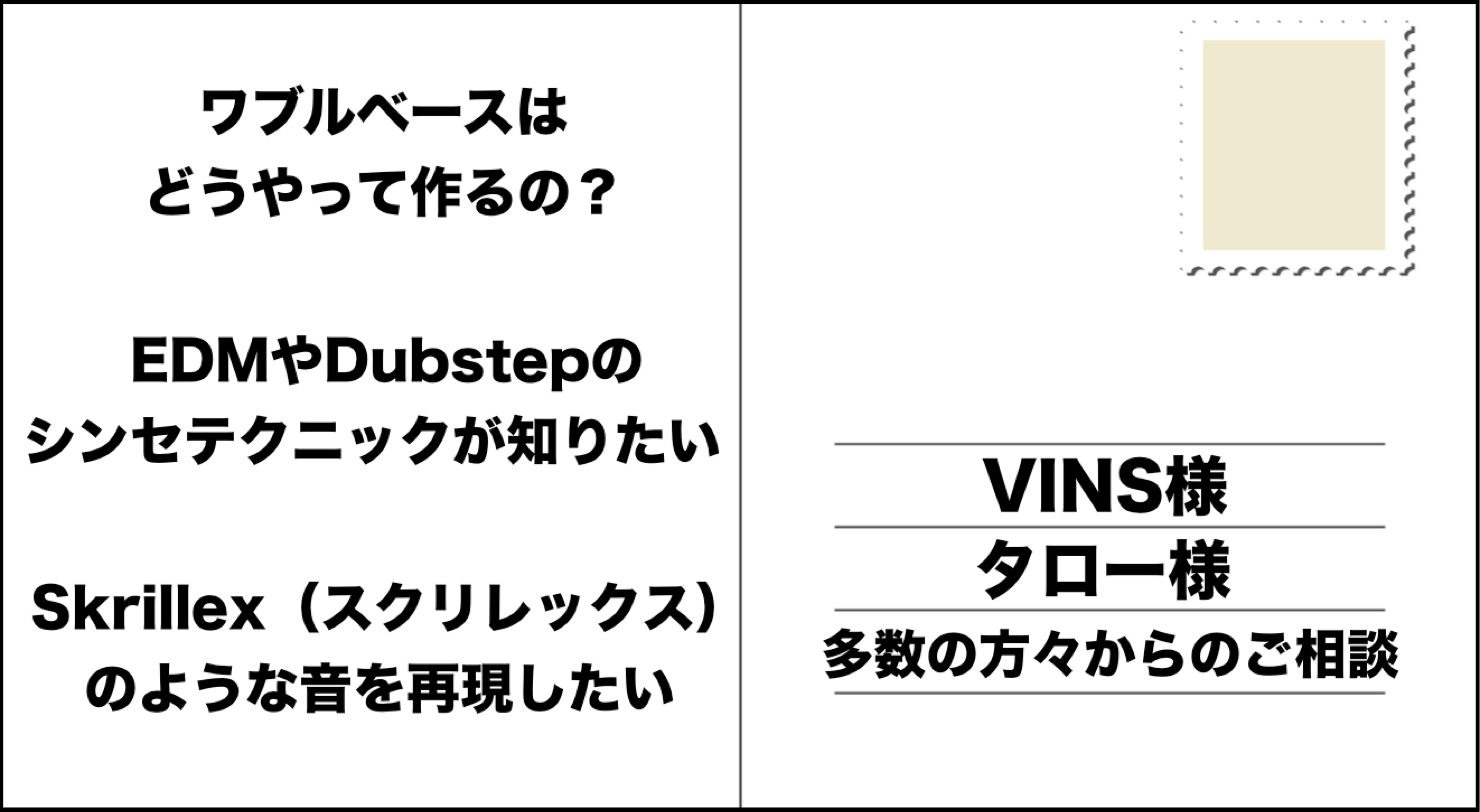
お悩み相談室へのAnswer動画「Skrillexのようなワブルベースを作る」第6弾、最終章です。
前回の続編となりますので、ぜひ併せてお読みいただければと思います。
最後も番外編ということで、MASSIVEのRingMod(リングモジュレーター)等を使った、ワブルベースと相性のいいシンセサウンドをご紹介します。エンヴェローブをうまく組み合わせ、アタック感を出していくのがポイントです。
サウンド作成方法
Massiveの設定
ENV4の設定
アタック感を出し歯切れの良い音とするため、以下のような設定とします。
- Attackは最速
- Levelは最小、Decayは11時くらい
- Releaseはやや長め
VOICINGとRestart via Gateの設定
音を太くするため、VOCINGタブでUnisonoを16とします。
OSCタブのRestart via Gateをオンにし、アタックを揃えて強調します。
OSCの設定
音作りのベースとしてクリアな音色としたいので、OSC1はサイン派を選択し、ピッチを2オクターブ上の24とします。
また1Envをピッチにアサインし、レンジを36としておきます。
1Envを上の画像のような設定としておくことで、音の出始めに、+36のピッチから+24へ瞬間的に落ちる音を表現することができ、これが音色のアタック感を演出します。
OSC2には低いピッチで、同様に1Envを使ってアタック感をつけておきます。
MODULATION OSCの設定
音に硬さを加えるため、RingMod(リングモジュレーター)を使用していきます。
対象はOSC1、ピッチを+36、RMツマミをあげると、金属的な硬い音色になります。
今回は、こちらにもエンヴェロープをかけてRMツマミを動かしてみましょう。
これで、最初に硬い音が出た後、Decayの時間をかけて効果が下がるという「さりげない硬さ」を表現できます。
NOISEの設定
打楽器っぽい雰囲気を出すため、今回はNOISEも混ぜていきます。
更に、こちらにもエンヴェロープを使って動きを加えます。
- NOISEのタイプは「Hi-Metalic」を選択し、Colorを2時くらいの位置にします。
- Ampには1EnvよりもややDecayが長く設定した2Envをアサインし、レンジはMAXにします。
これで、ノイズの音量は最大値から、Decayの時間をかけて下がることとなります。
FILTERとエフェクトの設定
OSC1,2そしてNOISEをF1に振り切っておき、以下のように設定します。
- FILTER1にLowpass4を選択し、上の図のような設定にします。
- FXでは、Classic Tubeを使用して音に太さを与えます。
また、今回は少し細かな設定を行いたかったので、DAW側でリバーブをかけています。
この辺りは、楽曲によってお好みで調整してください。
おまけ:ハイピッチサウンドの作り方
今回は最終回ということで、最後にもう一つ、こういったジャンルでよく見かける、高音域で揺れるようなサウンドをご紹介します。
基本設定
OSC1は少しSineから少しSquare側に振った程度とします。
マスターAmpのエンヴェロープは、お馴染みのAttack最速、Level最大です。
今回はマスターAmpにLFOもかけます。Sine波でRatioは1/12です。
エフェクトは、INSERTでParabolic Shaper、FXでClassic Tube、Small Reverb、EQ(ハイ上げ)をかけておきます。
Phaseによるピッチの調整
ハイピッチサウンドなのでOSCのピッチを上げると思いがちですが、それでは普通の高い音になってしまいます。そこで今回はMODULATION OSCのPhaseを使ってみましょう。
Global Tuneによるピッチの調整
更に、MASSIVE本体のチューニングであるGlobal Tuneを操作して、もっとクレイジーな音を目指してみましょう。
ハイピッチなので、Global Tuneを上げれば良いかと思いきや、そうとも限りません。
実は、Phaseをかけていることにより複雑な変調が起こり、Tuneを下げることでも高音を得ることができます。普通でない音を目指すならば、こちらの方が良さそうですね。
全6回に渡ってお送りしてきた「Skrillexのようなワブルベースを作る」のシリーズですが、いかがだったでしょうか?
ワブルにとどまらず、その他付随してよく出てくる音にも派生しましたが、このような様々な音の組み合わせによって、ダブステップ等の楽曲は構成されています。
ぜひ、様々な音色を学びながら、ご自身のオリジナリティも追求してみてください。