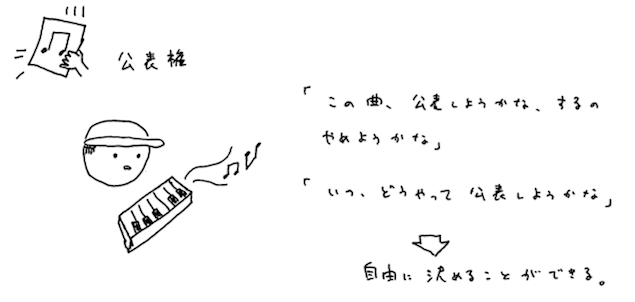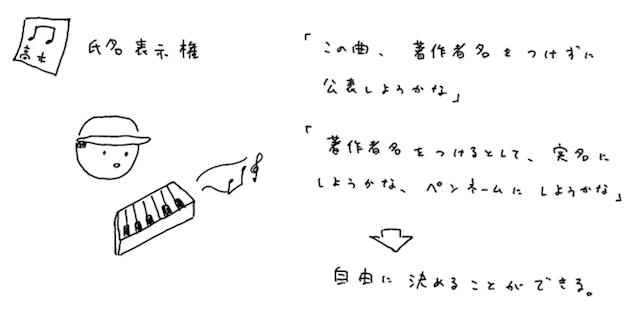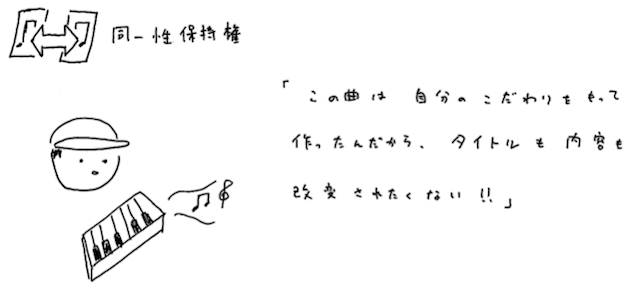著作権者人格権 音楽著作権
こんにちは。高木啓成です。
まずはちょっと復習です。
著作者の権利には、「著作権」と「著作者人格権」がある、
ということは、今まで何度も出てきましたね。
そのうちの、「著作権」の中身である「支分権」について、
前々回(第7回)と前回(第8回)で詳しく見ました。
今回は、「著作者人格権」の中身である、
「公表権」、「氏名表示権」、「同一性保持権」の
3つの権利を詳しく見ていきましょう。
著作者人格権は、特に、同一性保持権が重要です。
1 公表権(18条)
公表権とは、著作者が、自分の未発表の著作物を、公表するかどうか、
どのような形で公表するか、いつ公表するか、を決定することができる権利 です(18条)。
たとえば、僕が、ある楽曲を作曲したけど、出来があまりにも悪くて作曲家生命に関わると思い、
お蔵入りにしようと思っていたとします。
それなのに、勝手に、第三者に、
その楽曲を「作曲 高木啓成」として公表されてしまってはたまったものではありません。
ですので、著作者には、公表権が認められています。
ただし、未公表の著作物の著作権を第三者に譲渡した場合は、
その第三者に、公表を同意したものと推定されます(18条2項1号)。
ですので、たとえば、僕が、ある著作物について、
音楽出版社や音楽制作会社と著作権譲渡契約を締結した場合は、
公表について同意したものと推定されます。
音楽出版社や音楽制作会社は、
著作物を利用するために著作権を譲り受けているのですから、当然といえば当然ですね。
2.氏名表示権(19条)
氏名表示権とは、著作者が、自分の著作物を公表するに際して、
氏名をつけるかどうか、どのような氏名をつけるかを決定することができる権利です(19条)。
ですので、作曲者は、自分が作曲した楽曲を実名で公表することもできるし、
ペンネームで公表することもできます。
ある楽曲については実名で公表し、別の楽曲についてはペンネームで公表する、ということもできます。
3 同一性保持権(20条)
同一性保持権とは、
著作者が、自分の著作物のタイトルと内容について、
意に反する改変を受けないという権利 です(20条)。
たとえば、楽曲のBメロだけを勝手に変えたり、勝手に楽曲のタイトルを変えたりしたら、
同一性保持権の侵害になります。
それに加えて、楽曲に、勝手に別のアレンジを加えることも、
同一性保持権の侵害になると考えられています。
ですので、楽曲を無断で編曲することは、著作権の「翻案権(編曲権)」と、
著作者人格権の「同一性保持権」を同時に侵害する、ということになりますね。
ただし、著作者の意に反する改変といえども、やむを得ない改変であれば、
同一性保持権の侵害にはなりません(第20条第2項第4号)。
たとえば、テレビの歌番組では、楽曲の尺を変更して、
ワンハーフで楽曲を演奏することが多いですね。
これは、本来の楽曲を切り取っているので、同一性保持権の侵害になりそうですが、
テレビの放送時間の制約上、やむを得ない改変に当たると考えられています。
4 著作者人格権の不行使特約
著作者人格権は、著作者の精神的な権利なので、他人に譲渡することはできませんし、
相続によって相続人に著作者人格権が移転することもありません。
これは、第6回で説明しましたね。
ですので、たとえば、
僕が、自分の楽曲の著作権を取引先に譲渡したとしても、著作者人格権は僕がもったままです。
しかし、楽曲利用の方法によっては、取引先は、
「いつ、高木が著作者人格権を根拠にクレームを言ってくるか分からない。」と思い、
楽曲利用を躊躇するかもしれません。
そこで、取引先は、著作権譲渡契約書に、「著作者は、著作者人格権を行使しない。」という条項を
入れることが非常に多いです。
これを「著作者人格権の不行使特約」と呼んだりします。
「著作者は、著作者人格権を放棄する。」という条項も同じ意味です。
たとえば、音楽制作会社などから仕事の依頼を受ける際、著作権譲渡契約書に
このような条項が入っていることが多いと思います。
もっとも、みなさんが、音楽出版社に著作権を譲渡するときの
音楽出版社が使用しているMPA統一のフォームには、この条項は入っていません。
この条項が入っていると、著作者人格権の3つの権利が行使できない、
ということですので、十分注意してください。
もっとも、実は、著作者人格権の不行使特約という条項自体、無効だという考え方もあり、
確立した判例はありません。(音楽実務は完全に有効であることが前提で話が進んでいますが)
5 今回のまとめ
今回は、著作者人格権の具体的な内容を解説しました。
著作者人格権の3つの権利のイメージをもってもらえれば、と思います。
あと、著作者人格権は、著作権譲渡契約書で、
不行使特約が入っていることが多い、ということを憶えてもらえれば、と思います。
次回は、著作権が行使できない場合(著作権の制限)について、解説していきます。
著者の紹介
高木啓成
DTMで作曲活動中。
ロックバンド「幾何学少年」(現在、休止中)のリーダー、ドラマー。
弁護士として、エンターテインメント関係の法務、
中小規模の会社や個人の法律問題を扱う。
TwitterID : @hirock_n
Soundcloud : soundcloud.com/hirock_n
アクシアム法律事務所 : https://axiomlawoffice.com
- CATEGORY:
- サウンドクリエイターのための音楽著作権