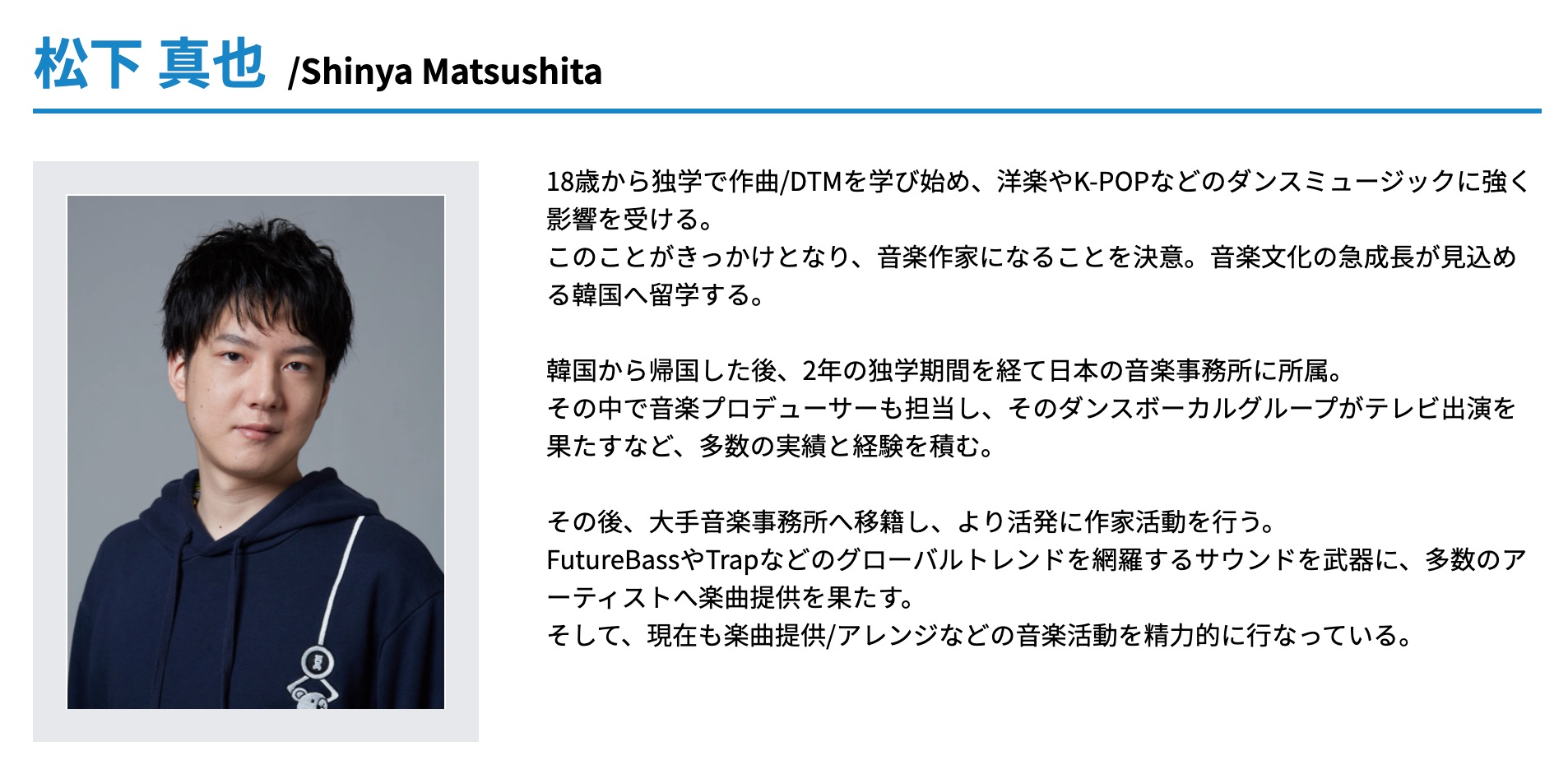Arturia「SQ80 V」リリース!ENSONIQ SQ-80をベースに進化を遂げたソフトシンセ
単純なモデリングにとどまらない Arturia「SQ 80 V」

Arturiaより、1988年に発売されたデジタルシンセサイザー「ENSONIQ SQ-80」をモデリングした「SQ80 V」がリリースされました。
モデリングシンセといえばMoogなどのアナログシンセサイザーが有名ですが、今回のモデリング元「SQ-80」はPCM音源を使用したデジタル方式のシンセです。
80年代後半に生み出されたそのサウンドは、ファットで抜けが良く、アナログとはまた違った華やかさもあるため、現在でも独特の地位を保っています。
そんなデジタルシンセサイザーの名機が、Arturiaによって忠実に再現されるとともに、使いやすく進化を遂げました。
ここでは主要機能をサウンドと共に解説していきます。
SQ-80由来の洗練されたユーザーインターフェースと音色
まずは、いくつかのプリセットをお聞きください。
1, デフォルトプリセット
2, ベースプリセットより [Classic Rolling 80's Bass]
3, リードプリセットより [Kradok]
Arturiaらしい高解像度かつきめ細やかなサウンドで、古臭さを感じさせない近未来感がありますね。
それでいて、アナログシンセにも負けない太いサウンドを実現できるのも特長です。
このように多彩かつモダンなサウンドは、
現代の制作においても即戦力になることは間違いありません。
次に、メインインターフェイスを見ていきましょう。
ここでのポイントは、やはり本物のシンセサイザーを触っているかのような美しいビジュアルと、より簡素化され分かりやすくなった配置です。
画面上部にオシレーターやフィルターがあり、それぞれの下には、Octave、Level、Semi Tune、Fine Tuneがあります。
左にはMaster Volumeの他、実機にはなかったArpeggiatorとUnison、Detuneが追加され、シンセサイザーの基本を知っている方なら直感的に操作できるものばかりです。
加えて、鍵盤上部の右側に隠されたパネルがあります。
ここには、ハードウェアにのみ存在する「音を鳴らすたびにランダムに変化する微妙な違い」を再現するための「分散」と言う機能が搭載されています。
これがサウンドに独特の”味”を与えてくれるわけです。
Arturia社ならではの、できる限り実機を正確に再現しようとする姿勢が伺えますね。
より自由度の高い音作りを可能にしたSynthesisとEffect
今回の音源はそれだけにとどまりません。
更に緻密な音作りを可能とするのが、画面右上にあるSynthesisとEffectのタブです。
Synthesisタブから見ていきましょう
こちらを開くと、キーボード的な画面から一転して、現在よく見られるウェーブテーブルシンセに似たUIに変化します。
実機モデリングシンセのわかりにくさを、見事にカバーしてくれる秀逸な機能ですね。
大まかな作りとしては、オシレーター、フィルターに加えて、エンベロープやLFO、さらに実機にはなかったMIXERが追加されています。
ここでまず特筆すべきはオシレーターです。
実機に搭載されている波形(SQ80 Waveforms)に加え、現在のウェーブテーブルシンセなどに見られる多彩なTranswaves、さらに実機に隠されていた波形(ESQ1, SQ80 Hidden Waves)が追加されています。
特にTranswavesの波形は、ウェーブテーブルシンセと同じようにPositionを動かすことができるので、かなり現代的な音色も作成できます。
次に注目したいのはMIXERです。
同じArturiaよりリリースされているシンセ「Pigments」にも搭載されている機能で、
LFOやエンベロープなどの好きな二つの波形を混ぜて、新しい波形を作ることができます。
オシレーターへ適用したり、Filterに複雑な動きをさせたりと、さらに音作りの幅が広がりますね。
最後に、Effectタブを見ていきましょう。
その名の通り、様々なエフェクトをサウンドに加えるセクションです。エフェクトは15種類用意され、最大4つまで同時に適用可能です。
ベーシックなReverb、Delay、Chorus、Over Driveをはじめ、 Tape Delay、Juno Chorusなどの少し独特なテイストを持つもの、 さらにCompresserやMulti Compresser、EQ、Stereo Panなどミキシング寄りのエフェクターも搭載されています。
加えて、Effectを直列でルーティングするか、2-2の並列でルーティングするかを下部スイッチで切り替えることが出来ます。
これにより、例えばリバーブを掛けた後の音にのみ歪みを加えるといったことも可能になります。
このように、実機には当然搭載されていない現代的な機能が取り入れられていることから、「SQ80 V」がただのモデリングシンセではないことがお分かりいただけたかと思います。
シンプルなモデリング系のソフトシンセは、出音は太いものの、作成出来る音色の幅は限られるため、現代の複雑な音作りに対応できないという難点があります。
そんな中でこの「SQ80 V」は、実機の独特なサウンドを忠実に再現しつつ、機能的な弱点を克服したハイブリットなシンセと言えます。
そこから生み出される新たな音色の可能性に、ぜひ触れてみていただければと思います。