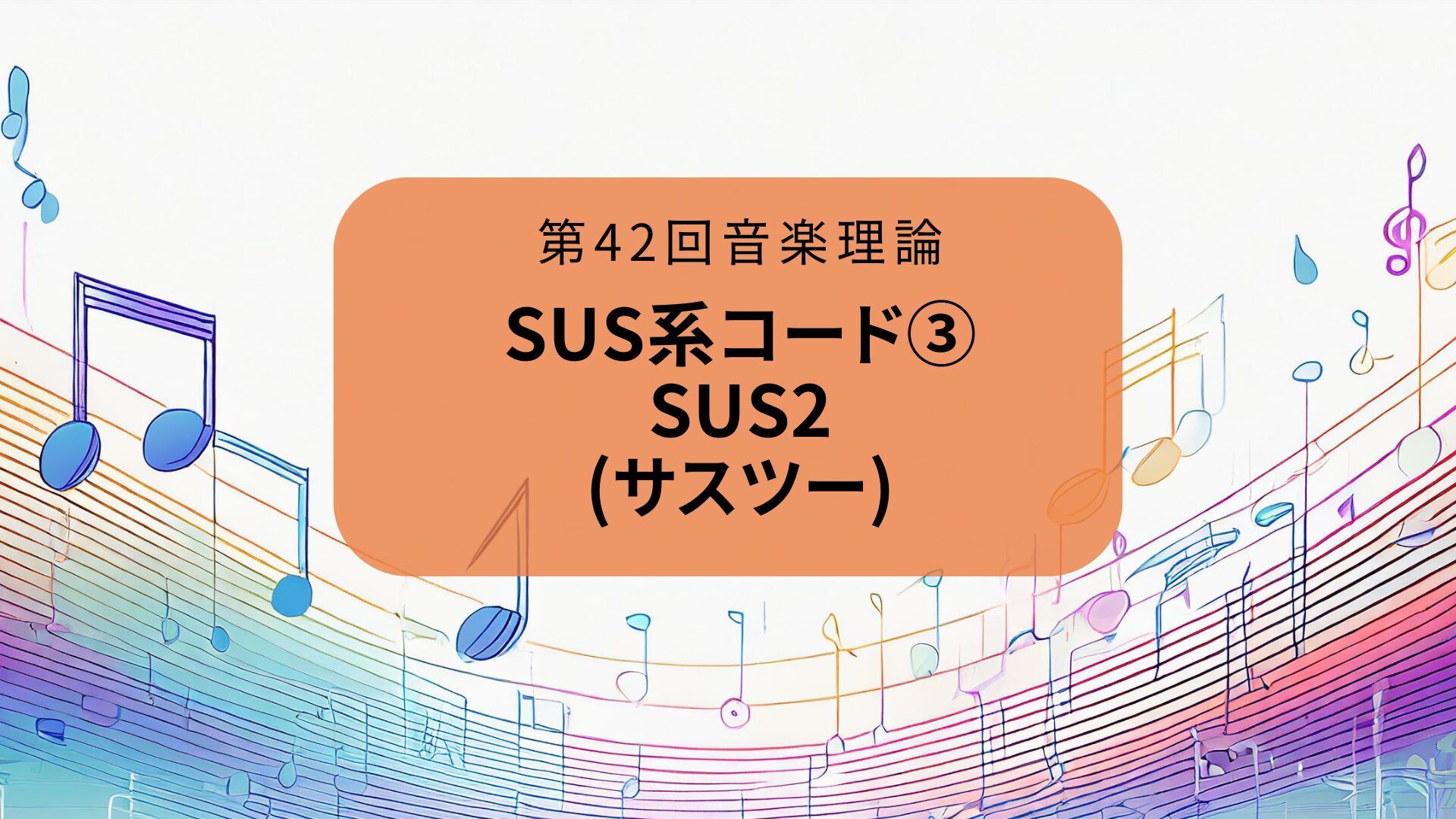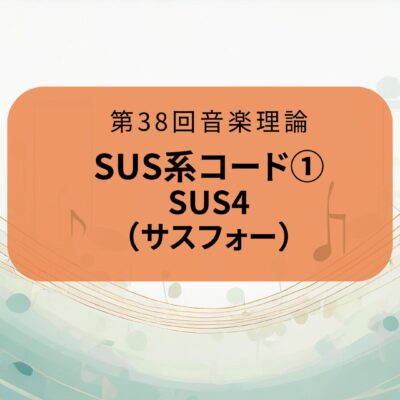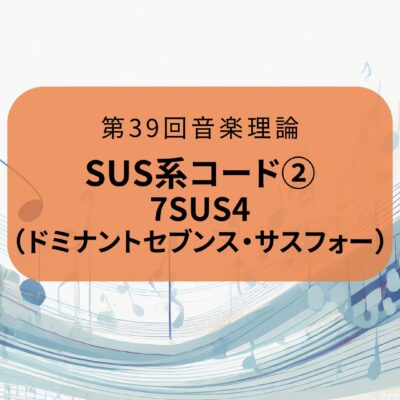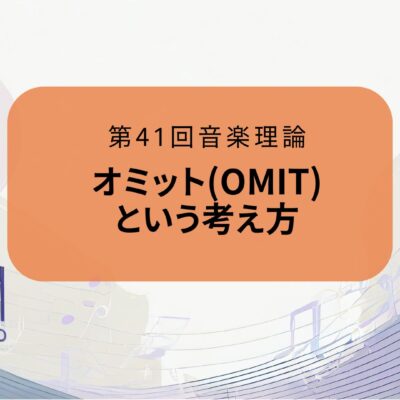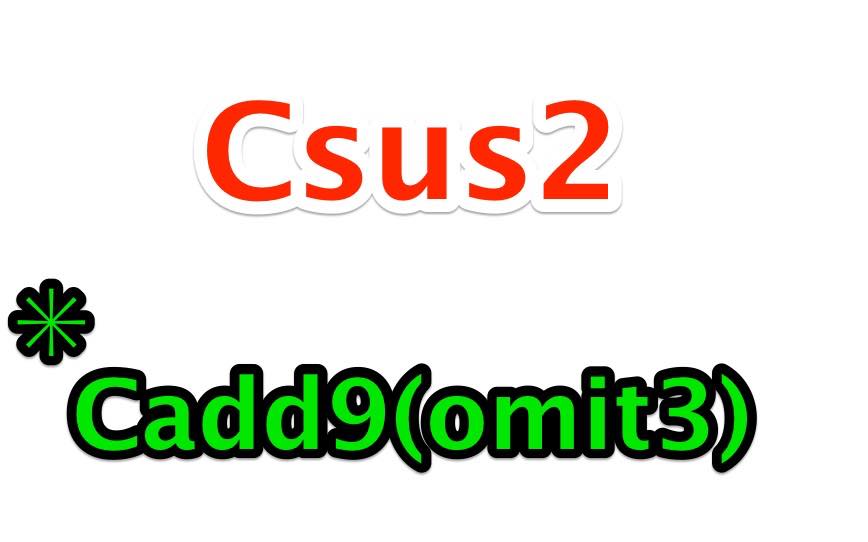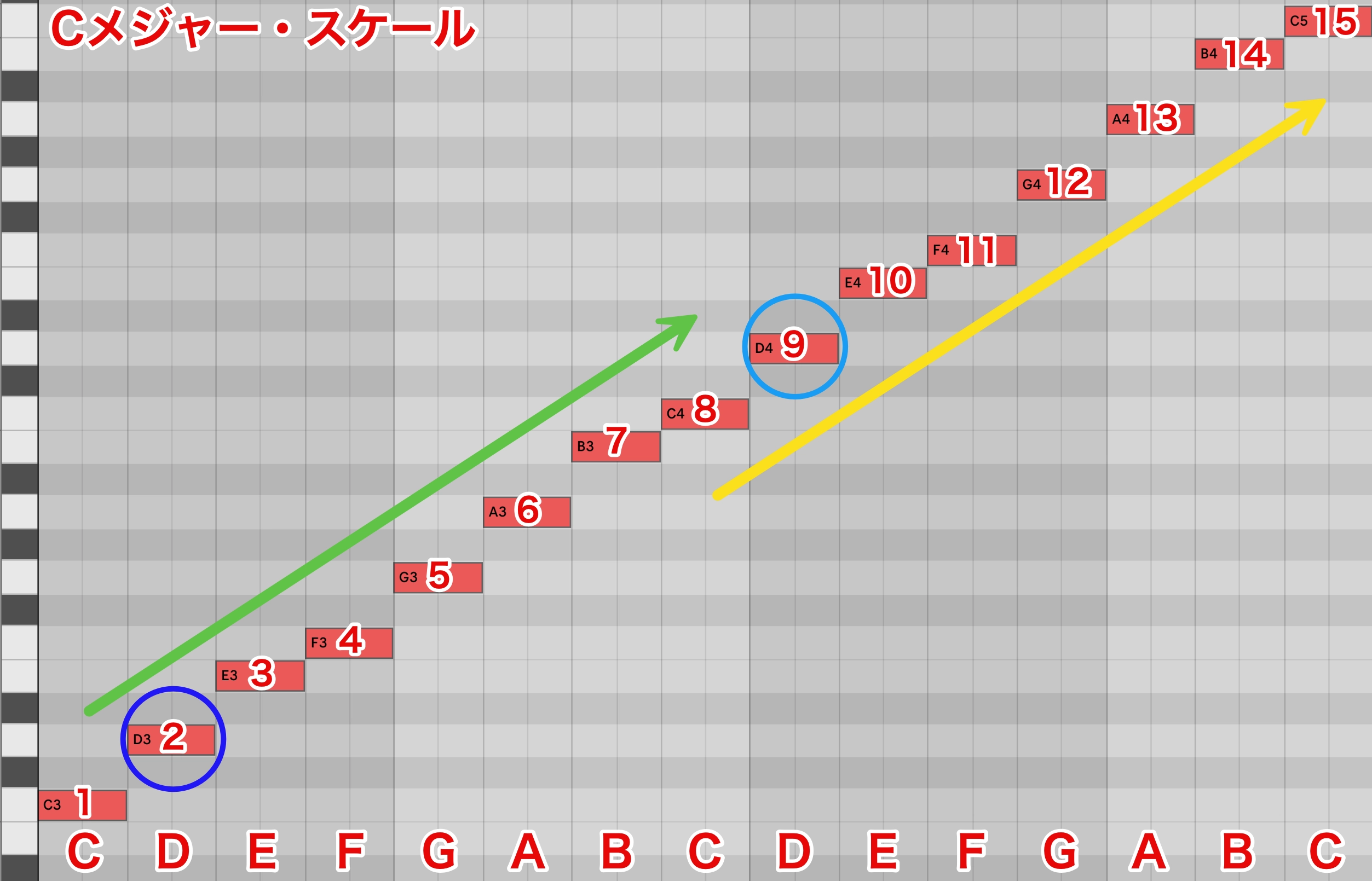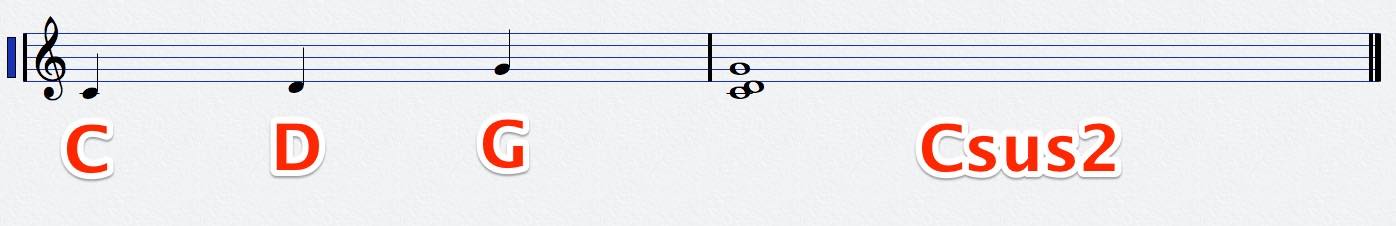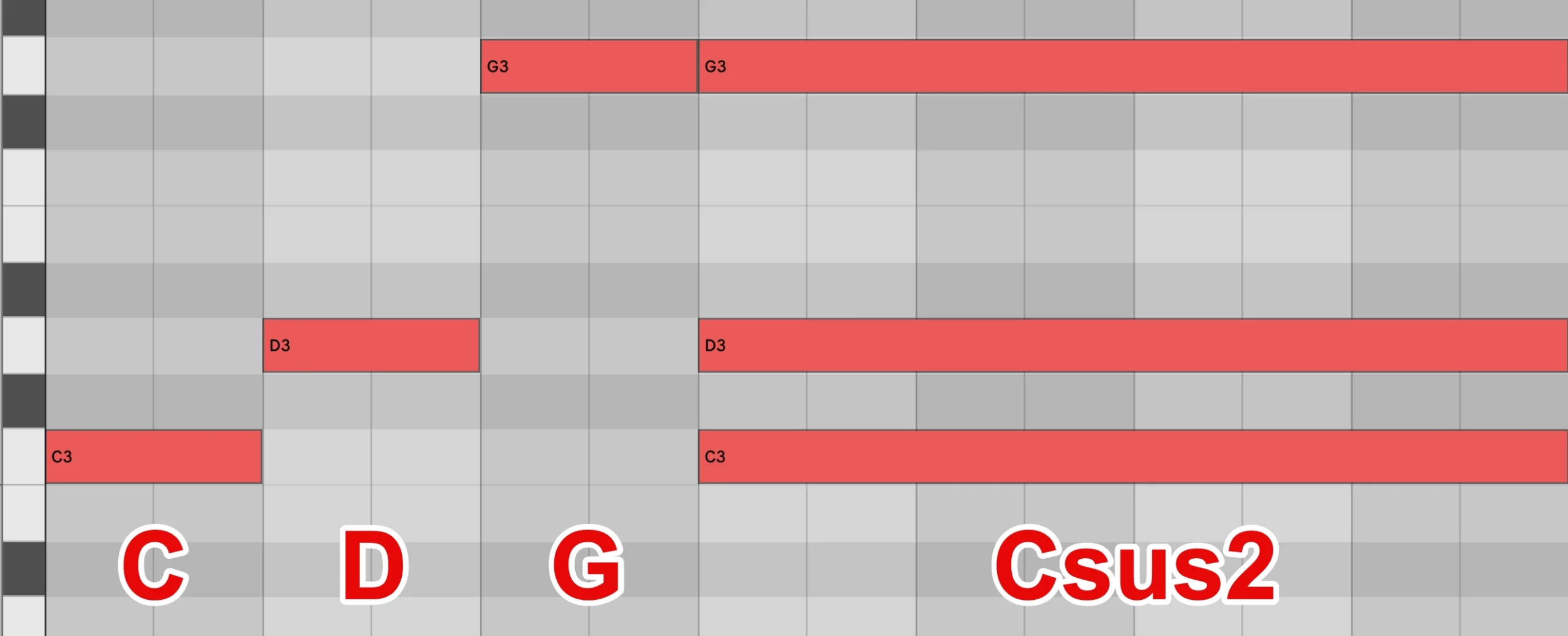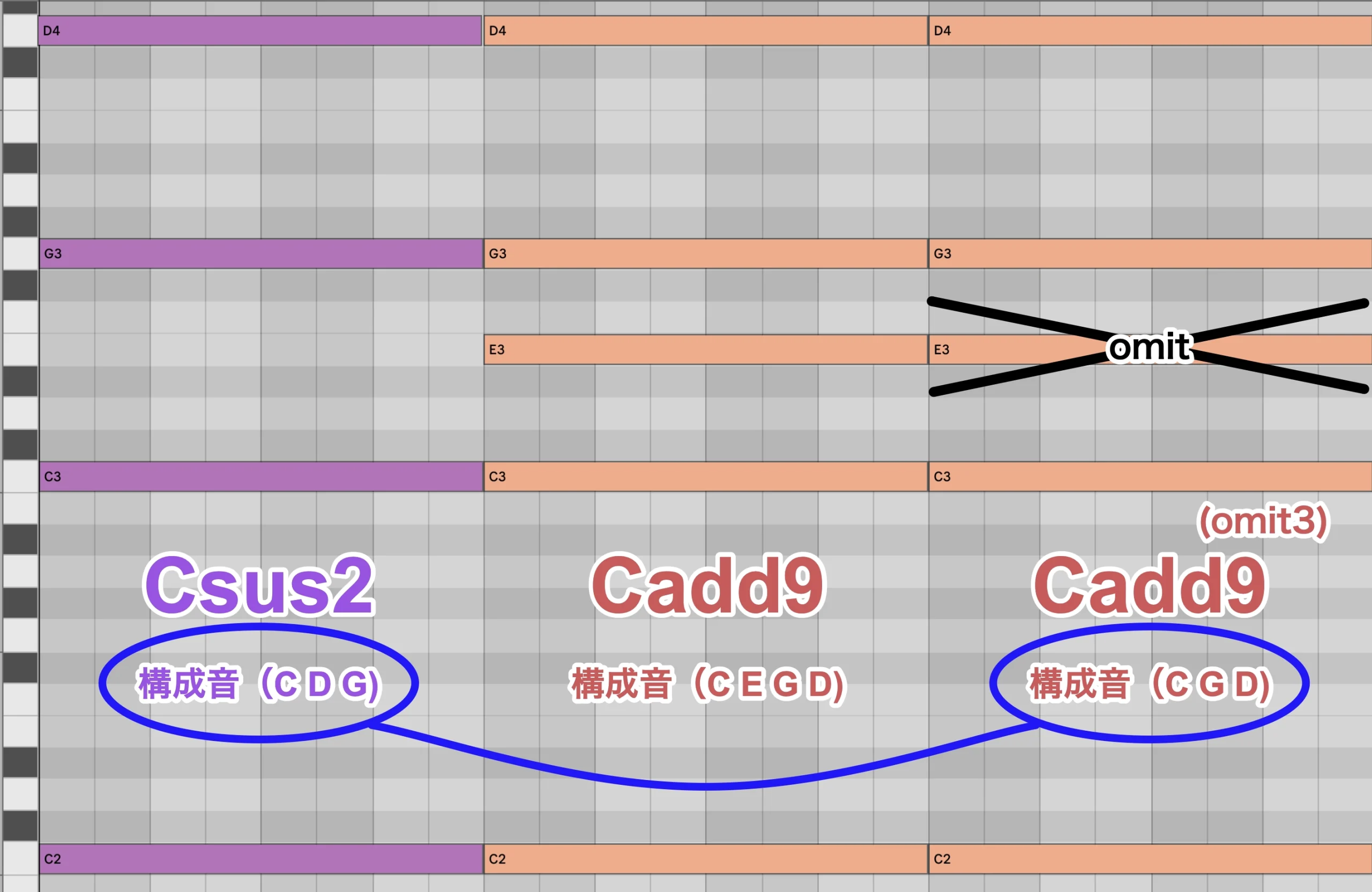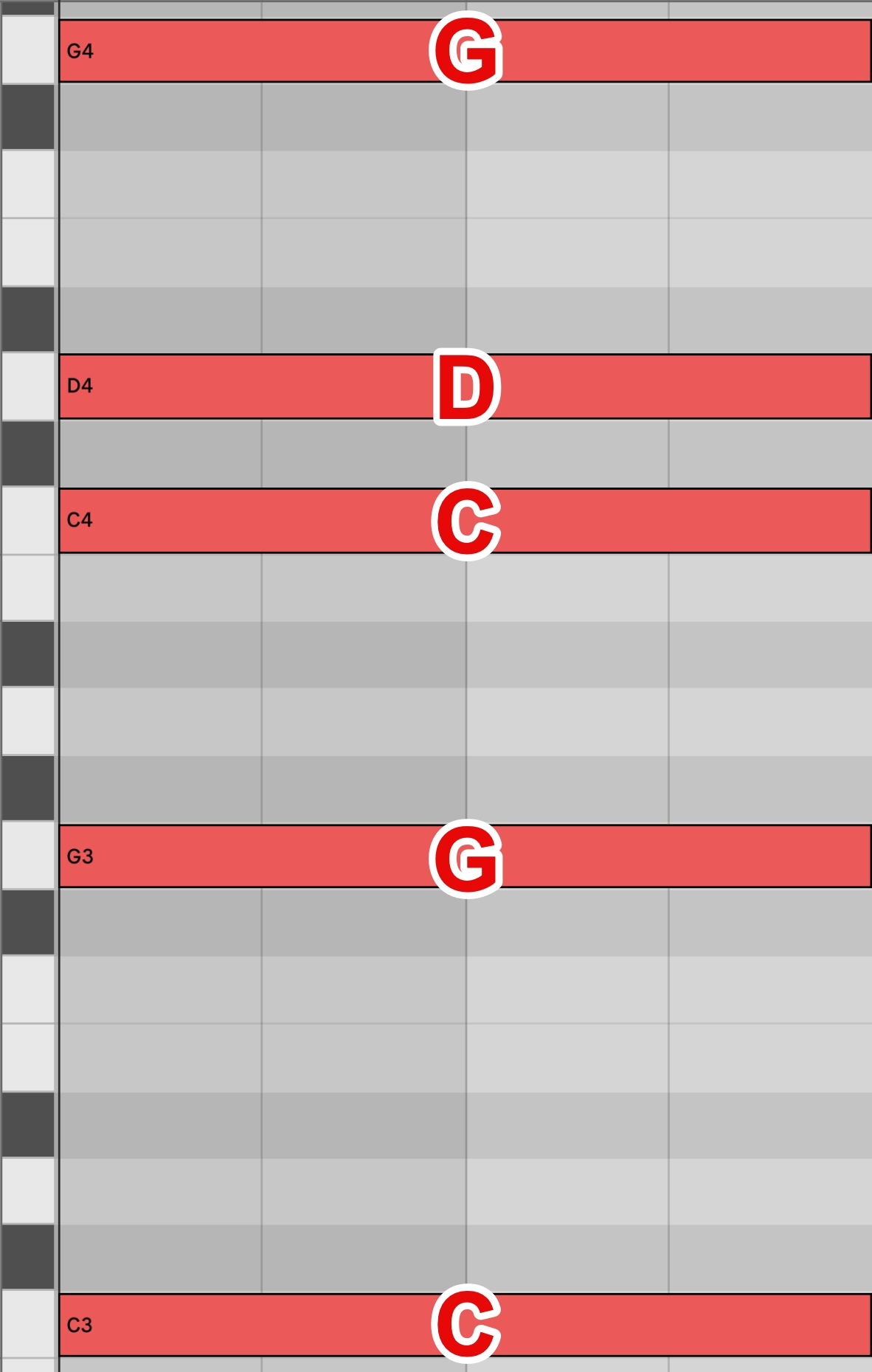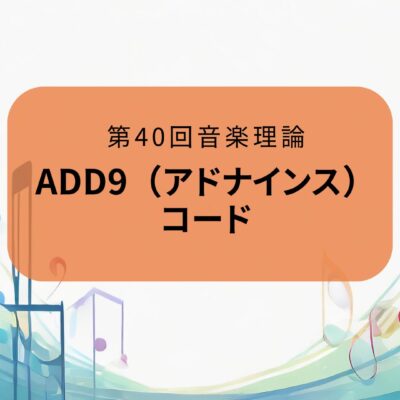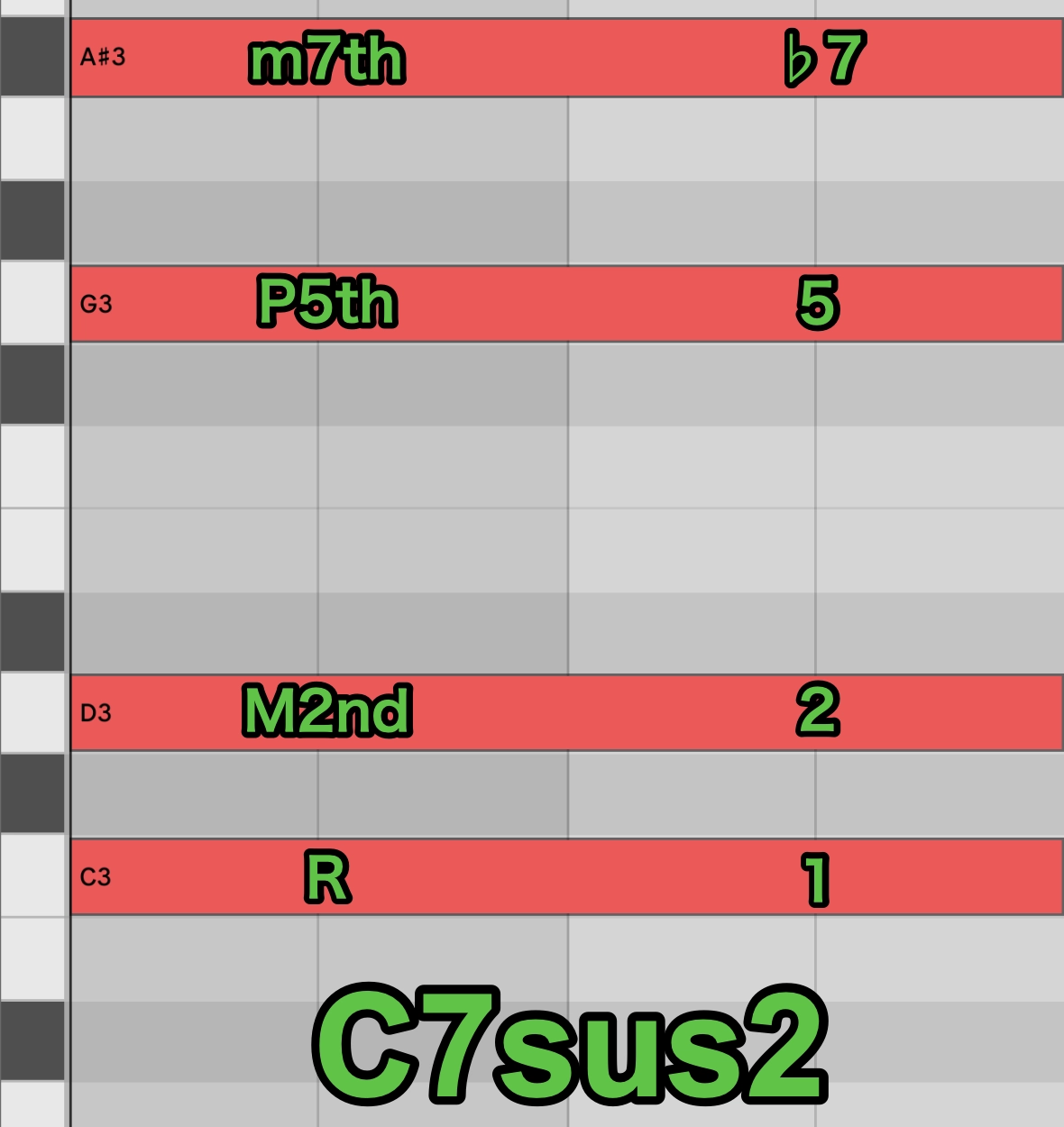sus系コード③ sus2(サスツー)/音楽理論講座
サスツーコードの概要
今回は、比較的新しいコード、「sus2(サスツー)」について学んでいきましょう。
以前は見かけることはなかったようですが、近年ではWebサイトや書籍でも一般的に掲載されています。
DAW上でも見かけますね。
本項を理解するためには、sus4、7sus4、omitに関する知識が不可欠となりますので、未読の方は下記をご参照ください。
サスツーの響き
まずは、サスツーのサウンドを確認してみましょう。
コードの構成音を順に鳴らした後に、コードが鳴ります。
- Csus2
先にお伝えしておくと、sus2はsus4と同様に、3rdの音(m3rd、M3rd)がないのが特徴です。
明るい・暗いとは分けられず、クールな響きに感じます。
他のトライアドのコードと交互に聴いて比べてみましょう。
- C→Csus2→Cm→Csus2
サスツーの表記
サスツーの表記にはほとんど種類がありませんが、少し特殊な表記法も存在します。
一般的には以下のように表記されます。
- Cサスツー= Csus2
- Eサスツー= Esus2
※Cadd9(omit3)に関しては後ほど説明します。
サスツーの成り立ち
また、「2」という数字が出てきましたね。
add9の回で使用したCメジャースケールの図を用いて、sus2の「2」に注目してみましょう。
Cメジャースケールの場合、2番目は「D」です。
既にお気付きの方もいらっしゃると思いますが、サスツーコードにはこの「2」の音が含まれます。
譜面とピアノロールで確認してみましょう。
他のトライアドのコードとあわせて、構成を確認してみましょう。
Csus2は、Cadd9のM3rdをオミットしたと捉えることもできます。
ただ、sus2の方が表記として短いため、使用されるようになったと思われます。
サスツーを使ってみる
サスツーの代表的な使われ方を見てみましょう。
- Fsus2→F→Csus4 →C
曖昧な感じからメジャーへの落ち着きが感じられますね。
- Csus4→C→Csus2→C
このように同じルートで、sus2とsus4を交互に使用するなどして動きを出す手法もよく見かけます。
次はメジャーやマイナーをsus2に変えてみた例を聴いてみましょう。
- 変更前 Am→G→F
- 変更後 Asus2→Gsus2→Fsus2
明るいとも暗いともいえない、クールな印象になりました。
以上のように、さまざまな使い方ができそうですね。
使用されている曲を見つけたら、前後のコードも含めて分析してみてください。
ギターにおけるsus2コードの考え方
上記は、ギターでよく知られるCadd9の押さえ方(ボイシング)ですが、実はこれはCsus2で、M3rdが含まれている押さえ方が、Cadd9じゃないの?などと言われることがあります。
M3rdがあるかどうかの違いですね。
他の楽器がM3rdを演奏していることでadd9が成立していたり、アレンジ上問題なければどちらでも構いませんが、ギター単体で明るさを強調したい、あるいは逆に抑えたい場合には、意識的に使い分けた方が良いでしょう。
ドミナントセブンス・サスツーについて
「ドミナントセブンス・サスツー(7sus2)」は、他のコードと解釈できるため、見かけることは少ないです。
ただ、前後のコードとの関係性を明確にするために、7sus2という表記が使用されるケースもあるようです。
もし見かけた場合は、以下のような構成になります。
次回は、add11(アドイレブンス)コードについて学んでいきます。