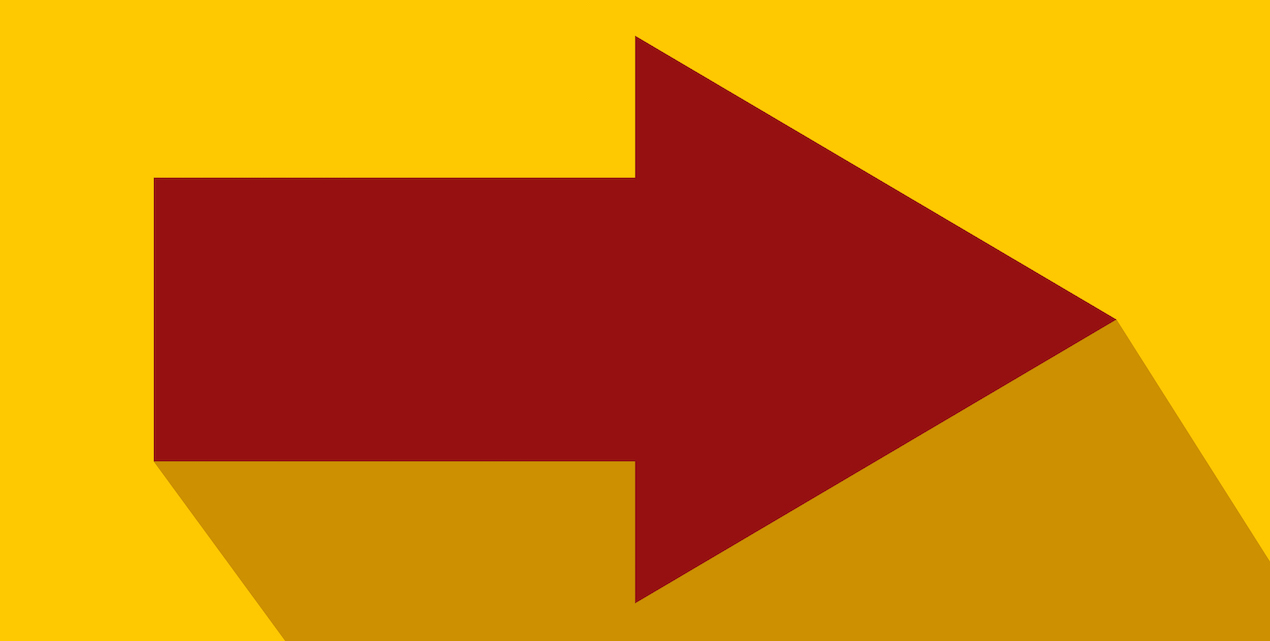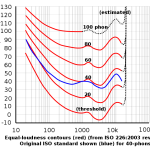コンペ楽曲の採用率を高める5つのポイント 音楽コンペ 楽曲採用の近道
楽曲の採用率を向上させるために
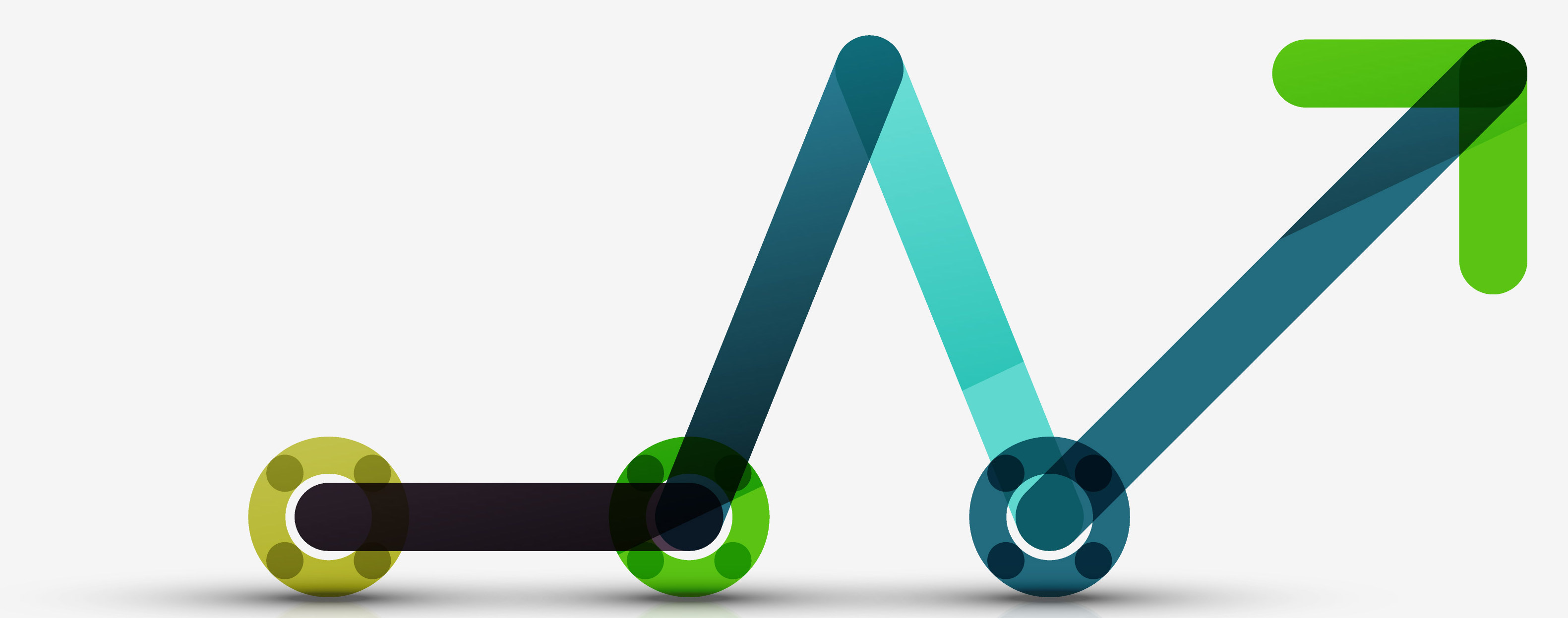
当然ですが、コンペに楽曲を提出するからには、採用を目指すことになります。
短期で考えると採用が運やタイミングに左右される場合もあるでしょう。
しかし、長期で安定した収益を考えた際に、大切となるスタンスは、
「採用確率を極限まで高める」ということです。
ここではコンペ楽曲の採用確率を高める5つのポイントを確認していきましょう。
曲に対して判断されるポイントを把握する
コンペ採用確率を高めるための最も効果的な方法は、
楽曲を「コンペに最適化する」ということに尽きるでしょう。
今回は、コンペ楽曲で意識すべきポイントを確認していきます。
ぜひご自身の提出楽曲へ取り入れてみてください。
1_方向性がブレない
コンペに限らず、お仕事としてとても大切な項目が、
求められていることをしっかり汲み取って、方向性から大きく外れないということです。
悪い例としては、下記ようなものが挙げられます。
- アップテンポな曲が求められている中でバラードを提出する
- 無理に個性を出そうと不必要な要素を詰め込む
- 楽曲途中でガラッと雰囲気が変わってしまい統一性に欠ける
これらはマイナスとなってしまう可能性が高いです。
意外に思われるかもしれませんが、参考楽曲に忠実に作成しても、
作家さんの個性や音に対するセンスは十分伝わります。
特に新人さんの場合、無理に冒険をせず、
忠実に進める方が良い結果に結びつくことが多いように思います。
2_曲として成り立っているか?を常に意識する
楽曲のクオリティーという意味で、ミックスや音色選びは確かに重要です。
しかし、もっと根本的に大切なことがあります。
それは曲として成り立っているか?楽曲自体は良いか?です。
- 歌モノの場合、メロディーは良いか?
- コード進行はしっかりしているか?
- 楽曲の展開が弱くないか?
これらに対して常に意識を置き、徹底的にこだわってみてください。
特に勿体ないと感じることが多いのは「楽曲の展開」です。
日本の音楽市場という特性上、
サビをしっかりと強く印象に残すということが重要になります。
サビを強く聴かせるための一例として
- 各A/B/サビのメロディーの譜割(リズム)に対しに変化をつける
- ドラムループに依存しすぎないように変化をつける
- サビへ繋がる「Bメロ」の楽器数を減らしてわざと落としておく
- メロディー/コードについて、サビに対する音程的な仕掛けをしておく
このように相対的にサビを強く聴かせる工夫が大切となります。
結果を出している作家さんの楽曲を分析してみると、この展開力に大きな差があります。
そのため、これらを意識するだけでも、楽曲が大きく変わってきます。
是非トライしてみてください。
3_仮歌は生歌を入れる
特に指定がない場合、シンセメロやボーカロイドでの提出でNGということはないですが、
仮歌は必須レベルであった方が良いです。
楽曲の表情が圧倒的に伝わりやすく、
楽曲を審査する側も、完成系のイメージが湧きます。
採用後、歌を入れたらイメージと全然違った、、
そのようなリスクも回避できます。
レコーディングやその後のエディット作業という仕事が増えますが、
これらの手間を考慮しても十分な価値があります。
4_サウンドをゴチャゴチャさせない
最近はトラック数に制限がないため、派手に聴かせようと過剰に楽器を入れてしまい、
全体的なイメージがゴチャゴチャしてしまっているケースを多く見受けます。
無駄に楽器数が多いと、ボーカルが薄まってしまうリスクもあります。
本当にこの楽器が必要か?ということを今一度考え、
ボーカルがしっかり立つことに一番意識を使ってください。
5_音圧は適度に
もちろん割れるほどに音圧を上げてはいけませんが、
音圧は適度にあった方が良いです。
コンペは様々な楽曲を聴き比べていくため、その中で音圧がないと、
どうしても楽曲のインパクトが弱くなってしまいます。
ボーカルがしっかり聴こえるよう、楽器のパンを適切に配置したり、
ボーカルと被る音域を軽くカットしておくと良いでしょう。
記事の協力 前川 敬(Kei Maekawa)
株式会社Grane(グラネ) 代表取締役
HP:http://grane-inc.com(作家を随時募集中です)
略歴:2005年より音楽業界にて作家マネジメントを担当し、2014年より独立。
現在まで多くの音楽作家の発掘・育成・マネジメントを行い、現在に至る。
マネジメントを担当した主な作家:
STY・HIRO・小田桐ゆうき・Carlos K.・若田部 誠・Hiroki Sagawa・鈴木まなかetc