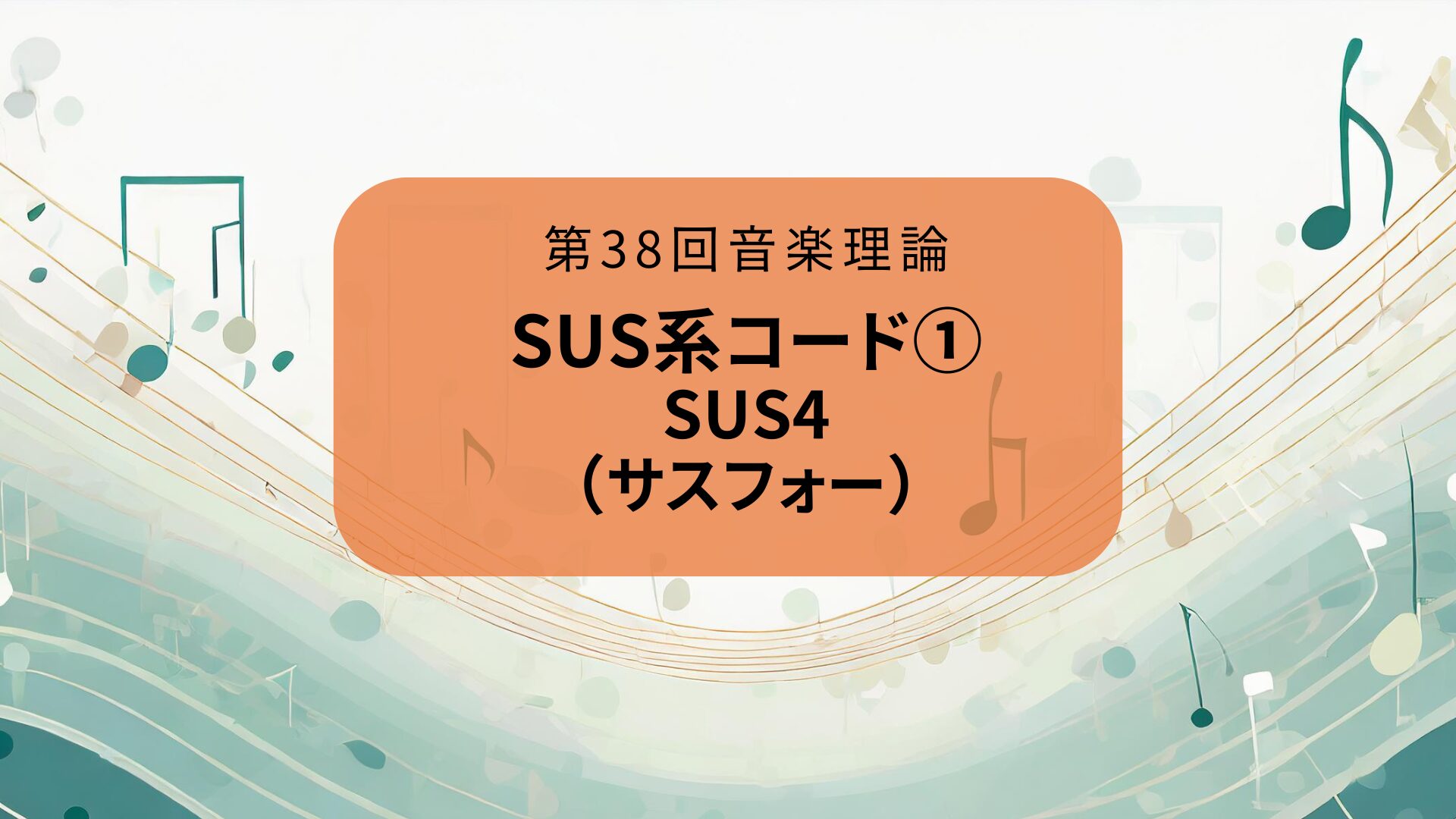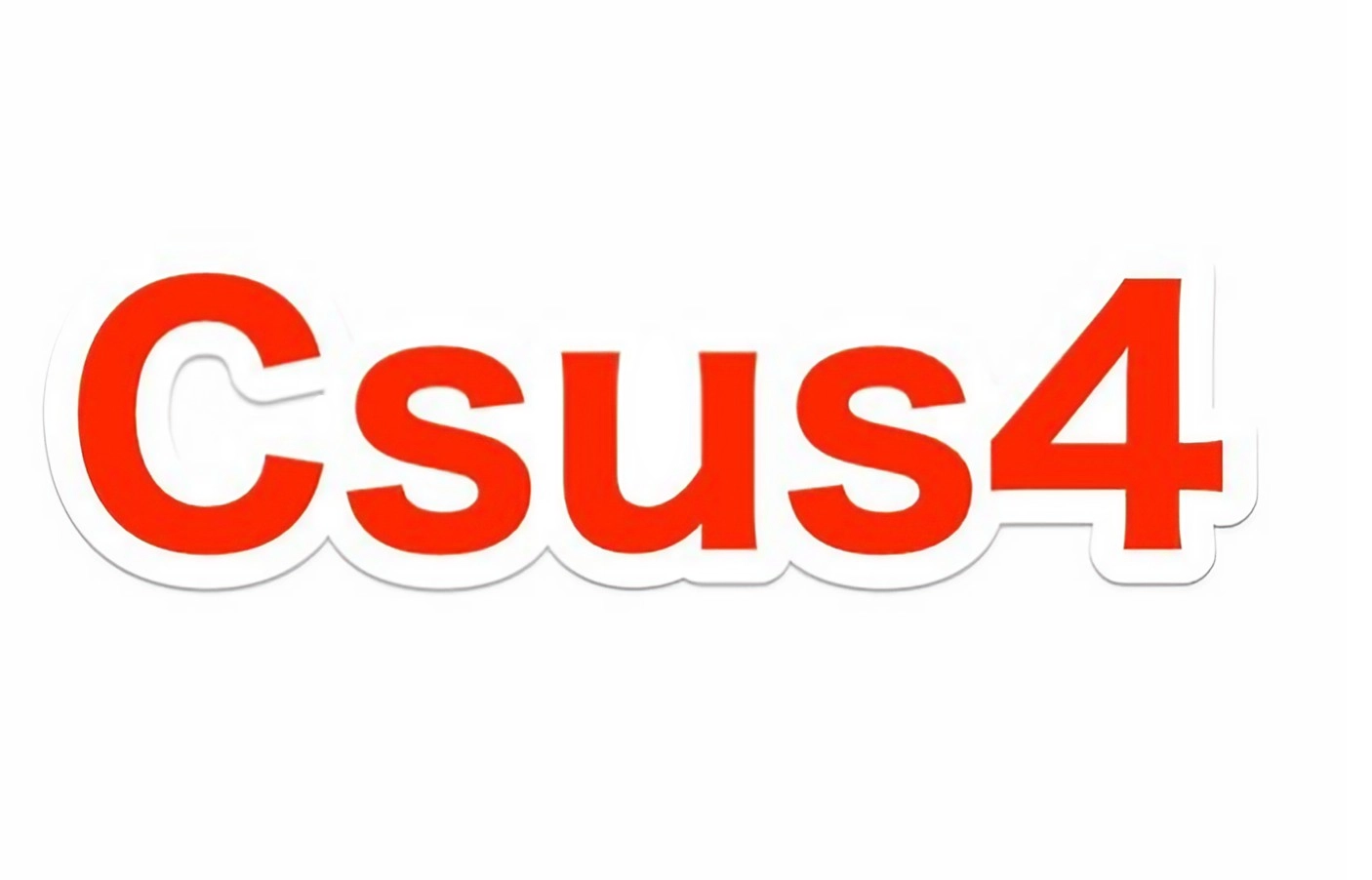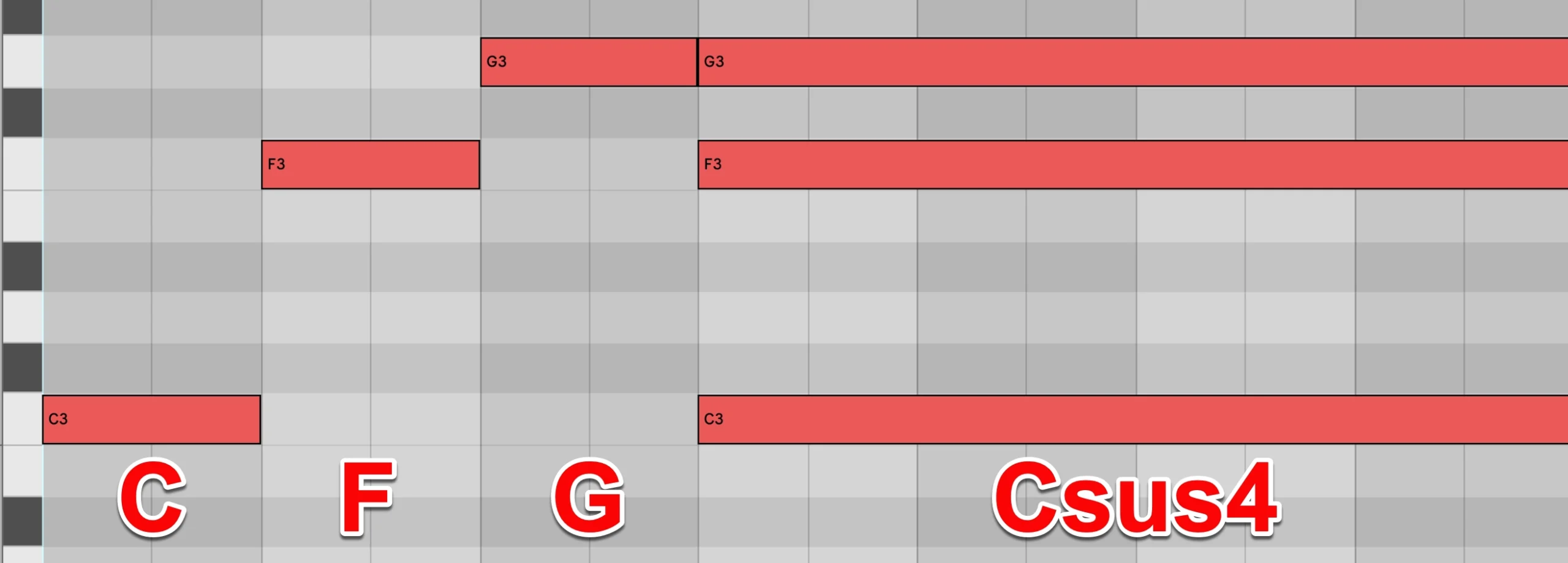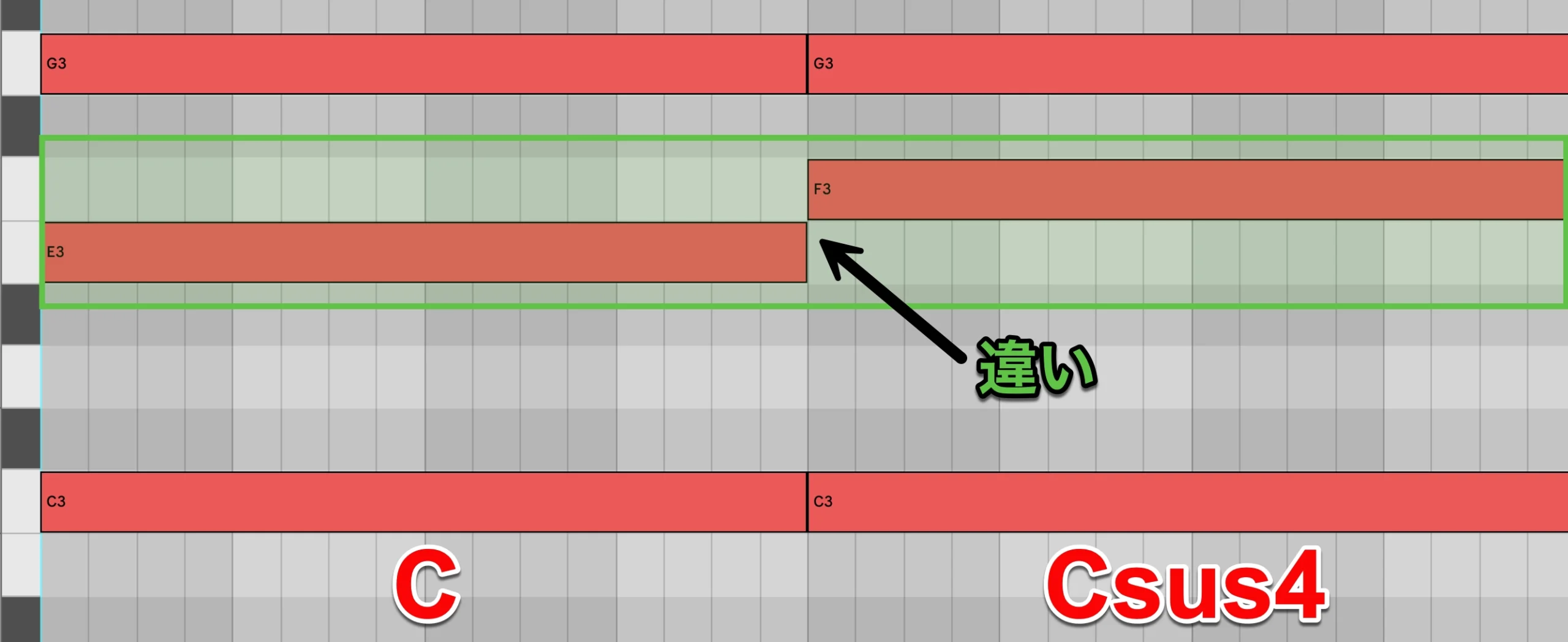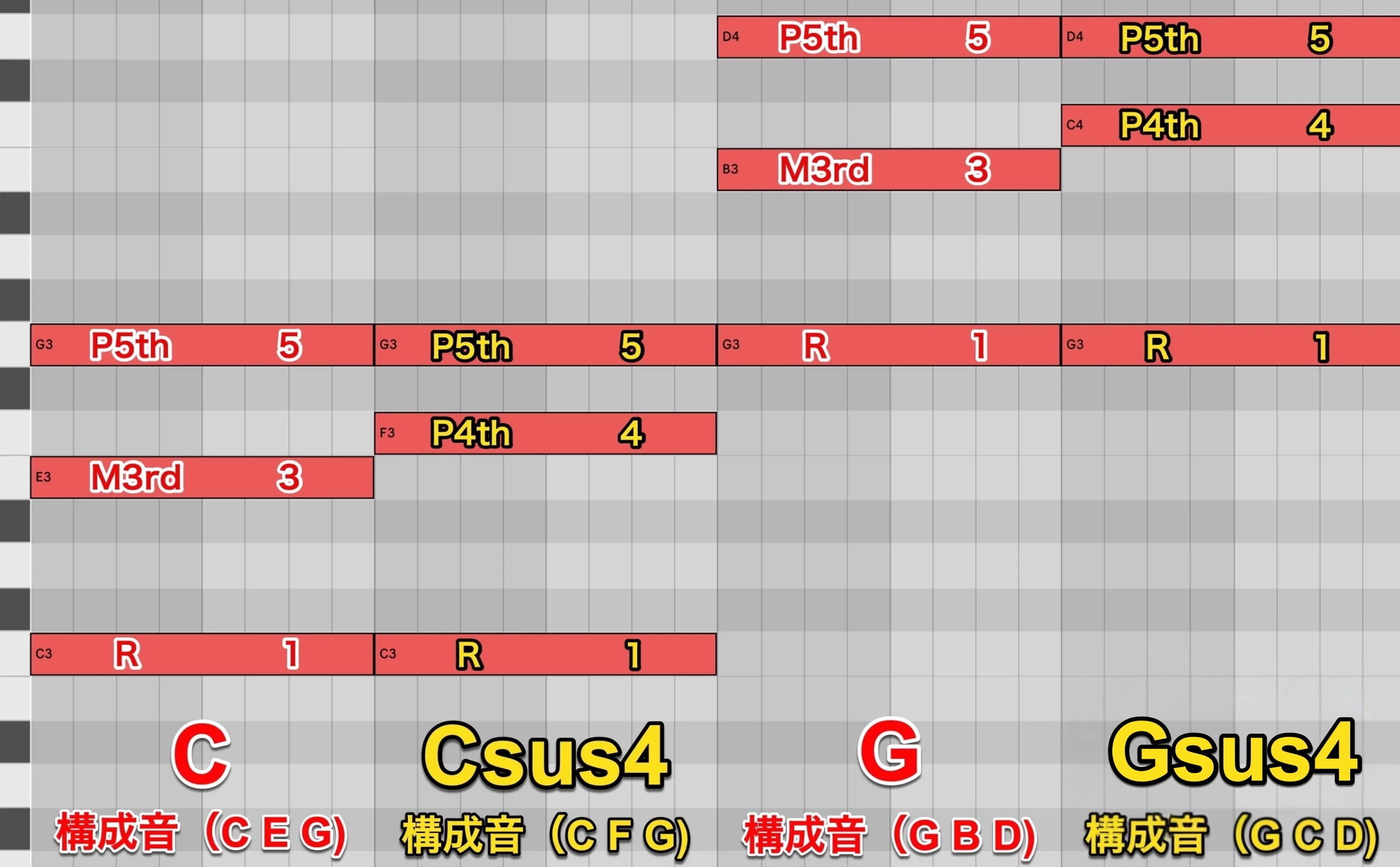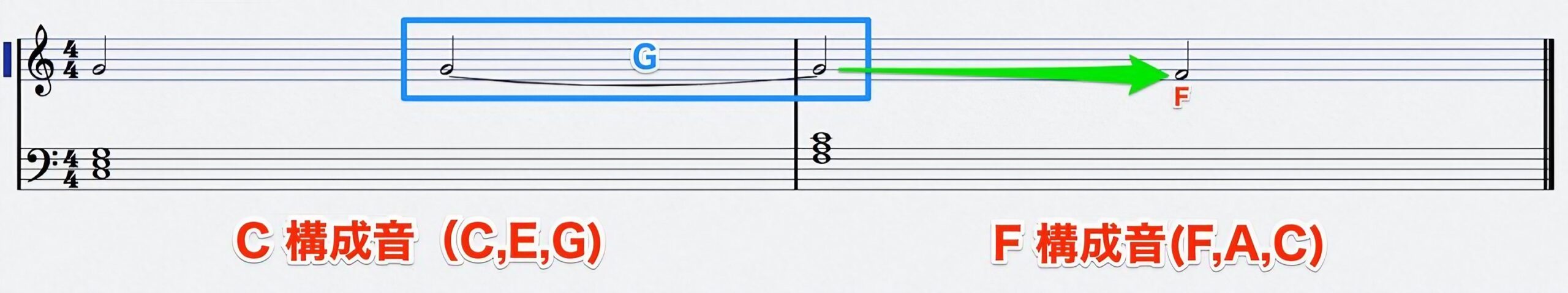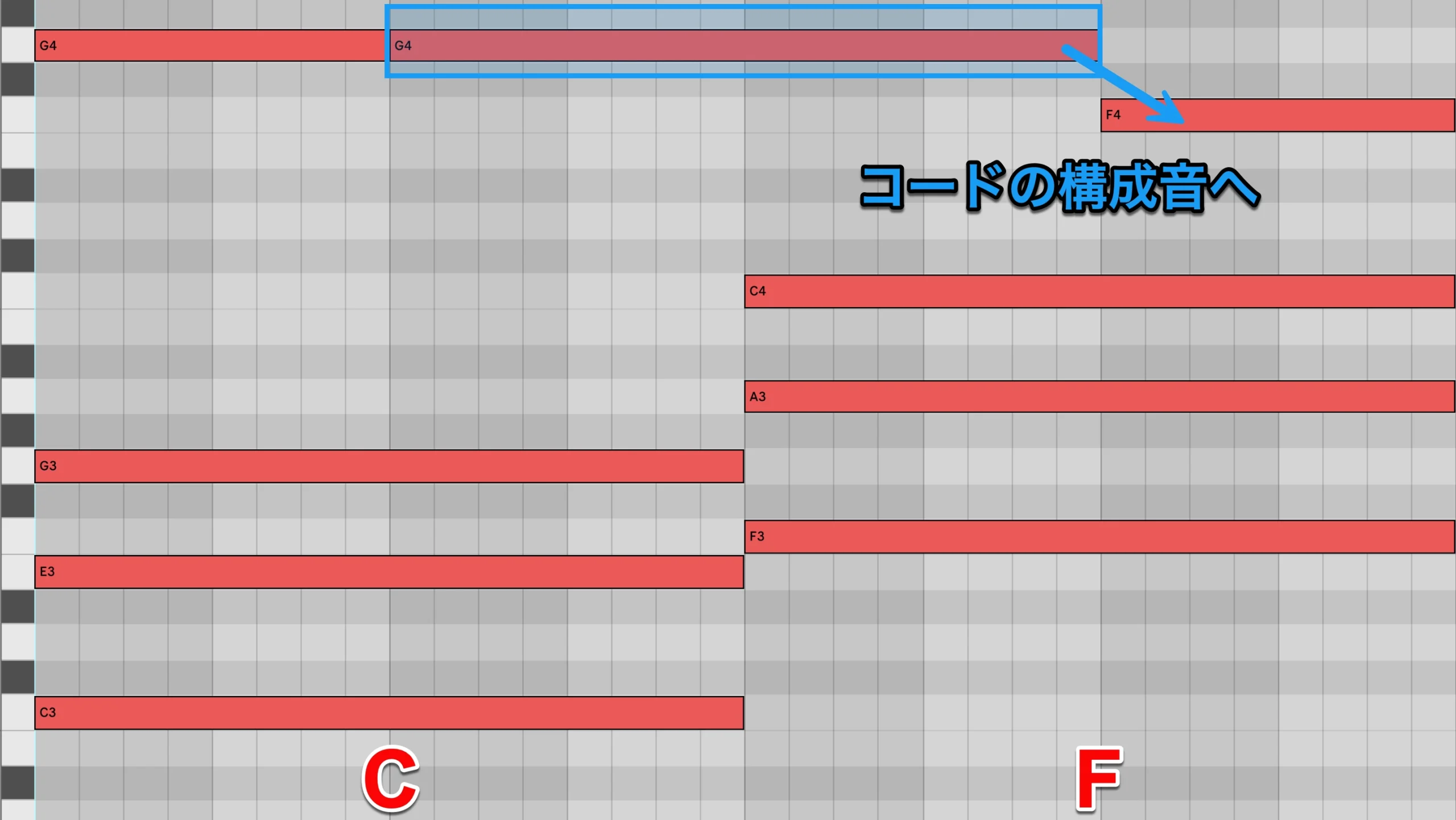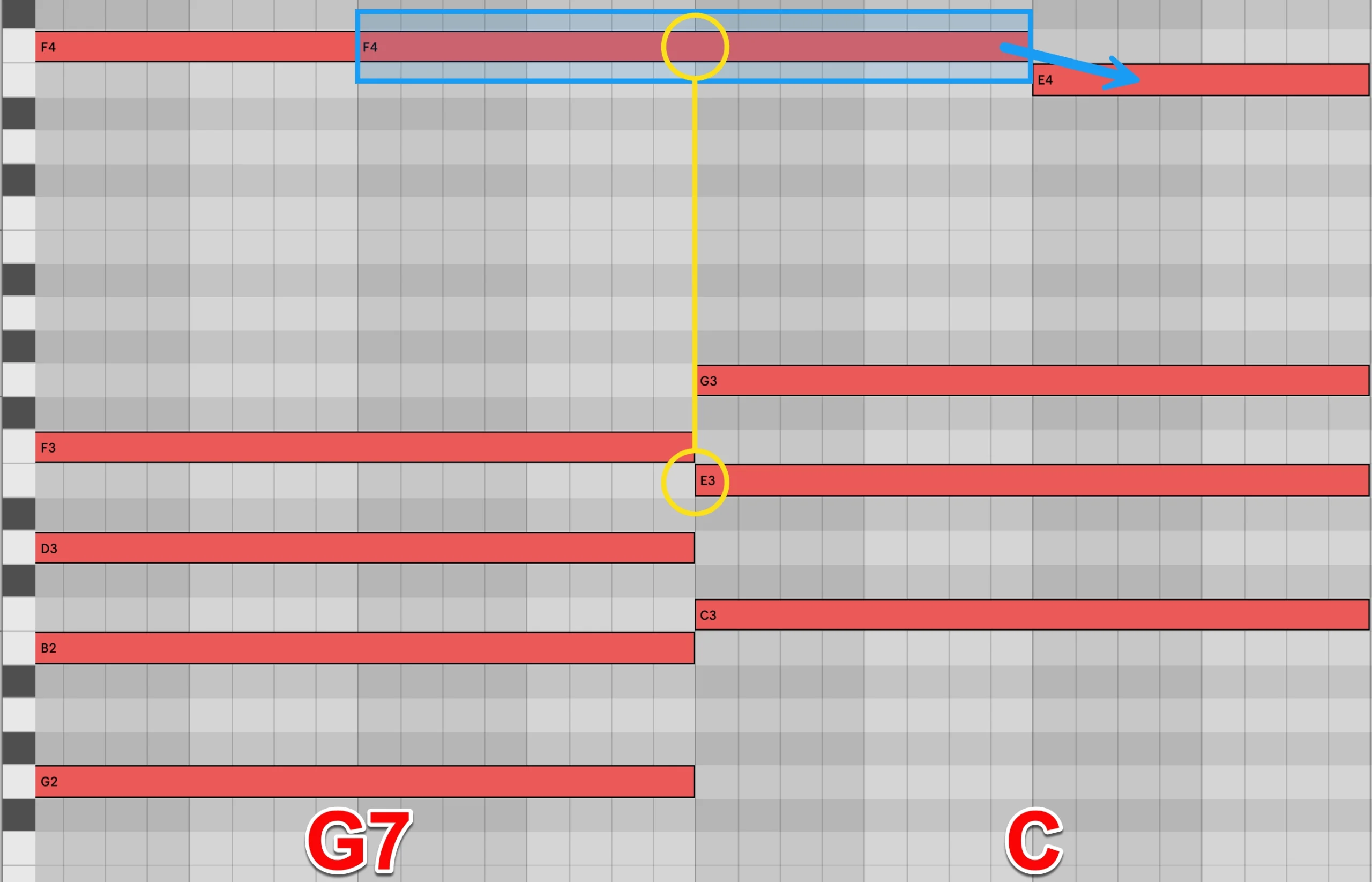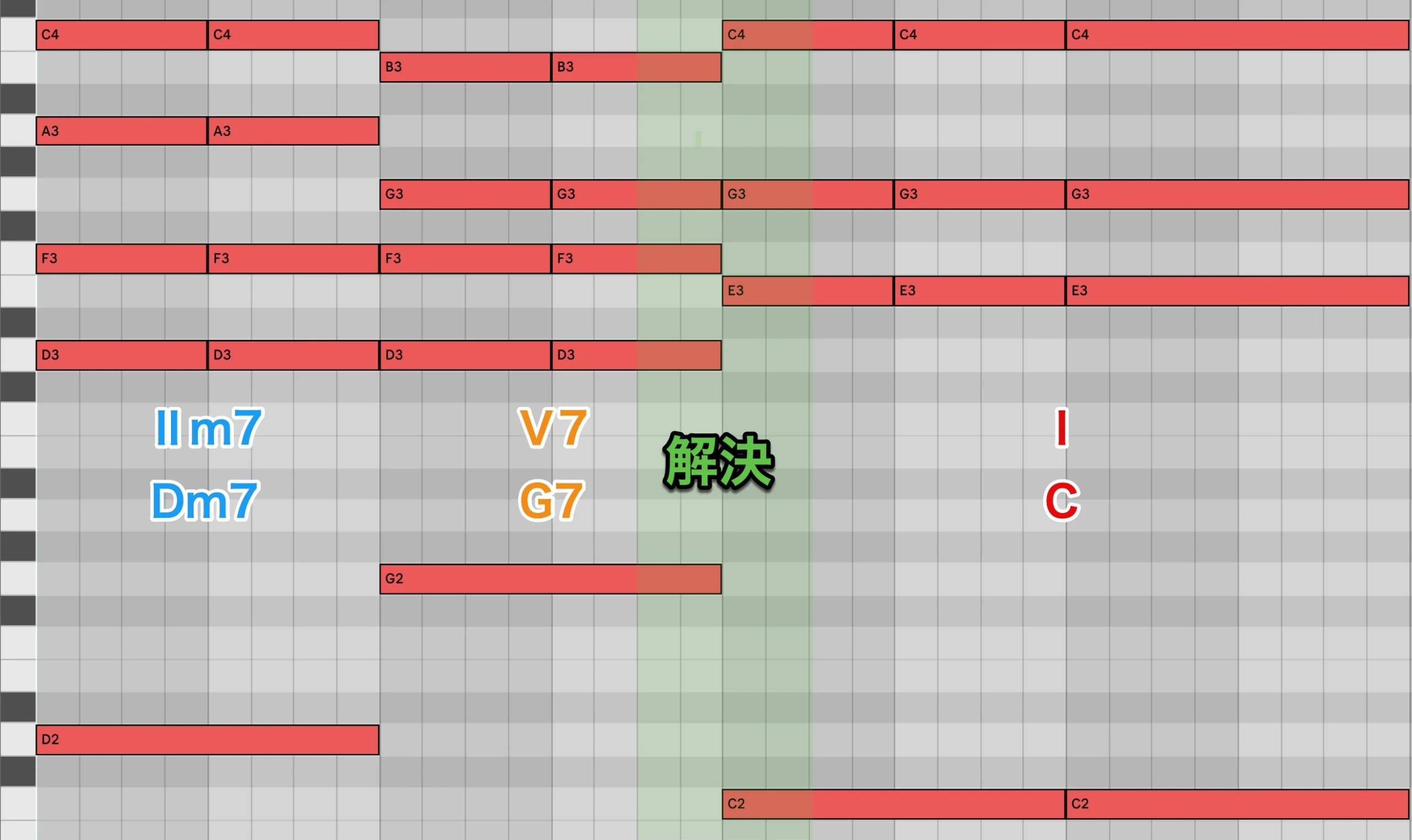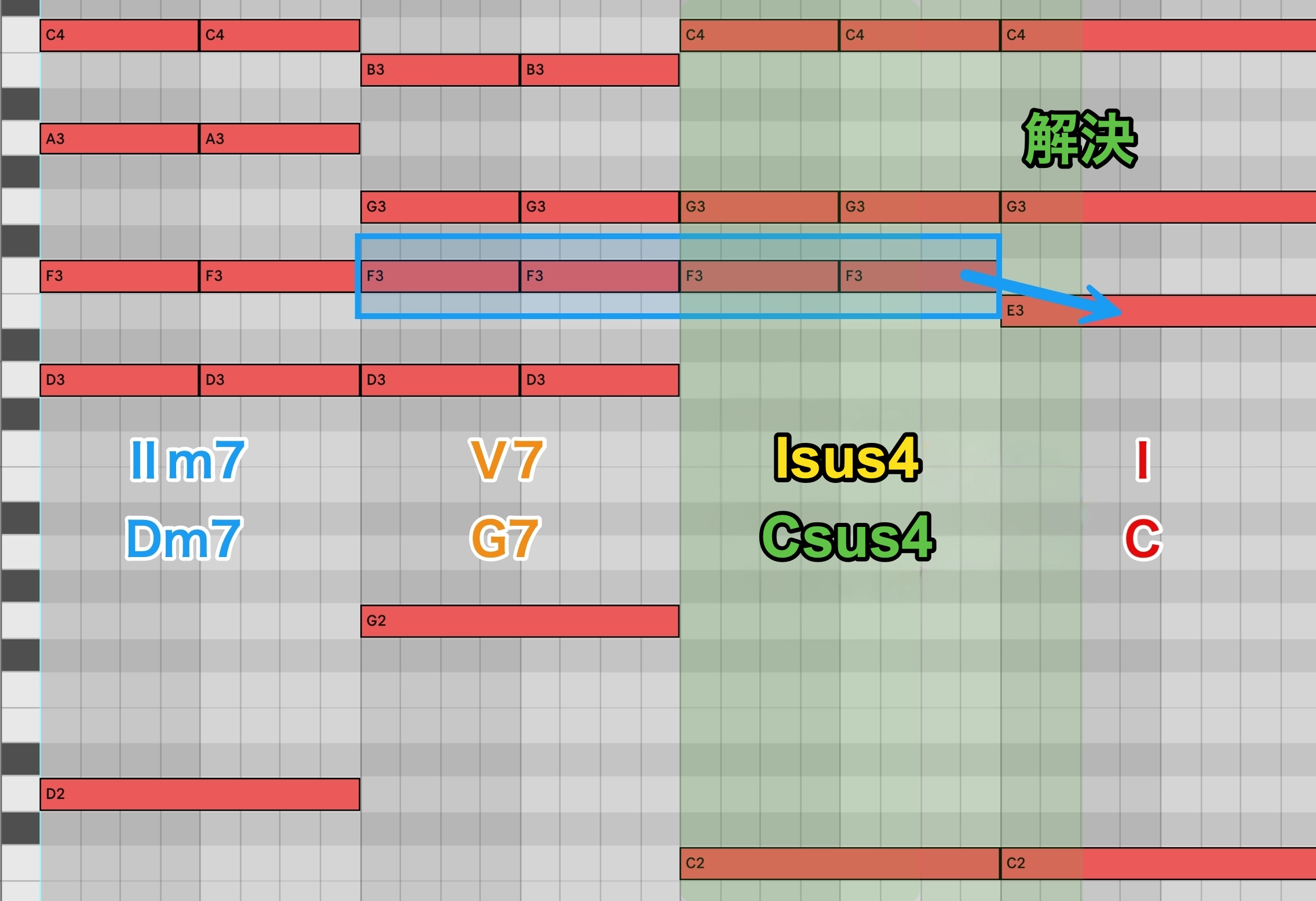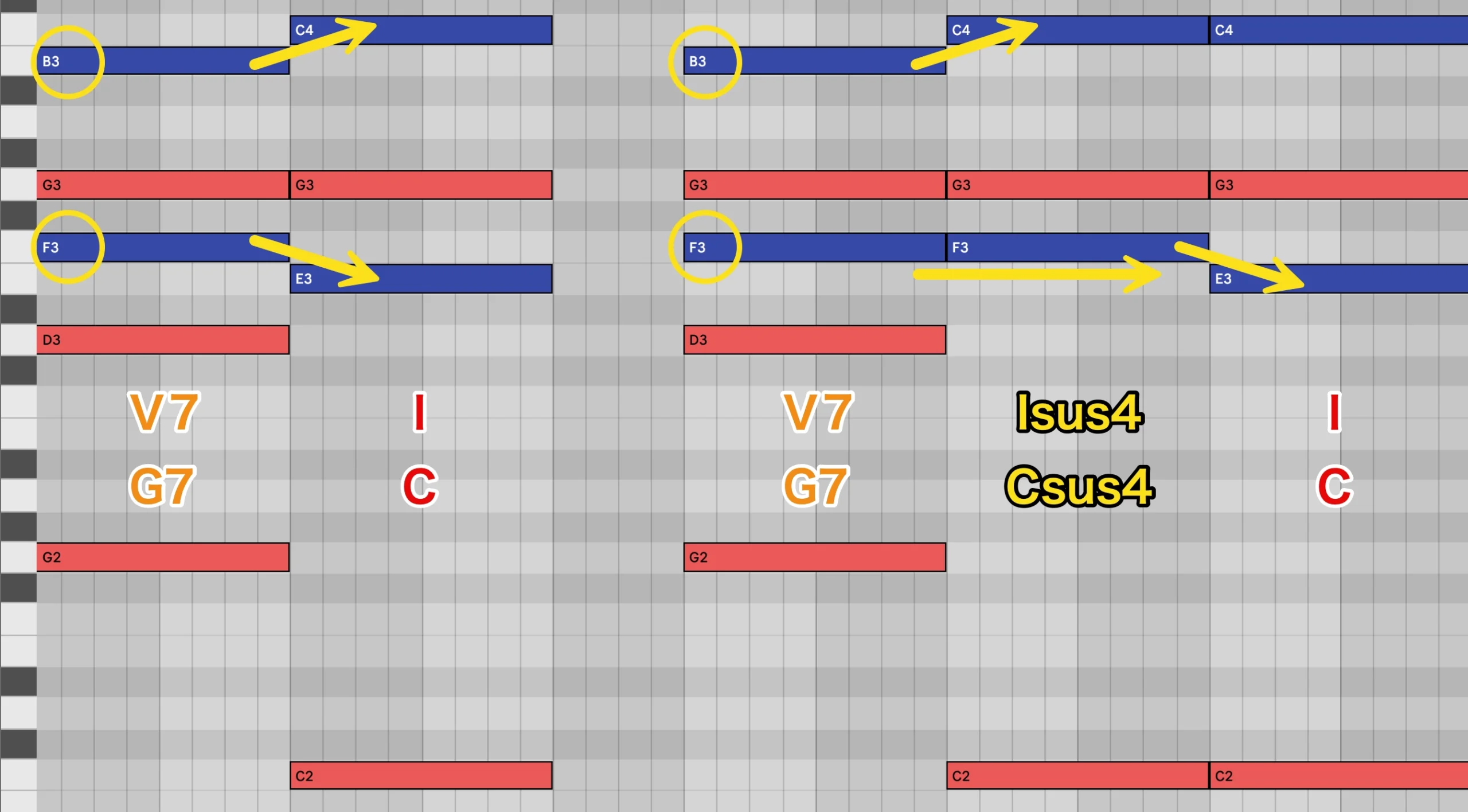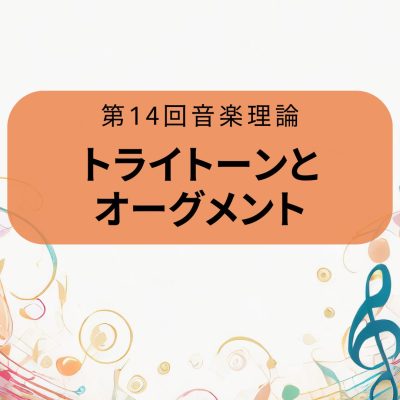sus系コード① sus4(サスフォー)/音楽理論講座
サスフォー・コードの概要
今回からsus系のコードということで、まずは“解決を遅らせる”ことができる、サス・フォーコードを学んでいきましょう。
コード進行の流れを変え、ドラマティックにすることもできます。
サスフォーの響き
まずは、サスフォーのサウンドを確認してみましょう。
コードの構成音を順に鳴らした後に、コードが鳴ります。
- Csus4
なんとも言えない浮遊感のある響きですね。
サスフォーの後に、Cメジャー・コードをつなげてみましょう。
- Csus4→C
浮遊感から解決したような印象もうけますね。
合唱コンクールを思い出した方もいらっしゃると思います。
サスフォーの表記
サスフォー・コードは、以下のように表記されます。
基本的にこの表記1つで問題ありません。
- Eサスフォー= Esus4
- Fサスフォー= Fsus4
サスフォーの成り立ち
Csus4コードの基本形を、譜面とピアノロールでそれぞれ確認してみましょう。
メジャートライアドの構成をマスターしている方は、M3rdのみの違いだと気づくと思います。
構成音は以下の通りです。
- ルートからのインターバルでは、R/P4th/P5th
- ルートを1としたスケールディグリーでは、1/4/5
となりますね。
サスフォーの意味
sus4は、「”suspended” fourth chord=“サスペンディッド”・フォース・コード」を略したものです。
ここで、「サスペンディッド・ノート(Suspended Note)= 掛留音(けいりゅうおん)」について学んでおきましょう。
サスペンディッド・ノートとは、「ノンコード・トーン(非和声音)」の一種で、コードの構成音ではない音を指します。
前の小節の旋律が伸びて(タイで繋がれて)次の小節にまたがる様子を想定してください。
その後、その音はコードの構成音に解決(主に2度)するイメージです。
G7→Cの進行でF音を伸ばした状態が、Csus4コードの元のイメージとも考えられます。
サスフォーを使ってみる
実際にサスフォーをケーデンスに取り入れてみましょう。
元のサンプルとして、下記のツーファイブワンの流れを使用します。
- Key=Cメジャー:IIm7→V7→I(Dm7→G7→C)
G7→Cの全終止(ドミナント・モーション)で解決していますね。
次に、G7→Cの間にサスフォーを加えてみましょう。
- Key=Cメジャー:IIm7→V7→Isus4→I(Dm7→G7→Csus4→C)
G7→Cの間にCsus4を加えることで、解決が遅れて聞こえ、最後のCでやっと解決した印象ですね。
G7のFが、Csus4のFと共通音になっている点にも注目してください。
m7の音が伸びているようにも捉えられます。
この場合のトライトーンの動きにも注目してみましょう。
二段階に分けて進んでいますので、解決が遅れるイメージと繋がりますね。
このように解決の前にサスフォーをワンクッション置くことで、終止をよりドラマチックに演出できます。
さまざまな曲で使われていますので、楽曲分析の際にぜひ注目してみてください。
次回は、他のsus系コードも見ていきましょう。